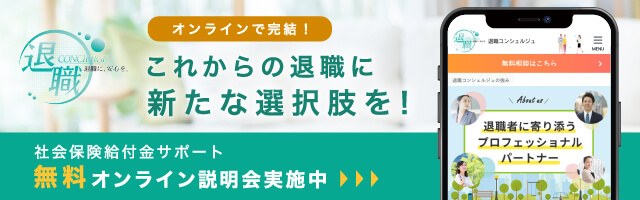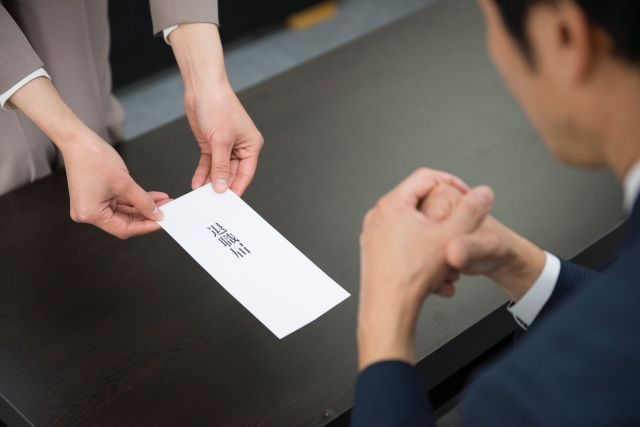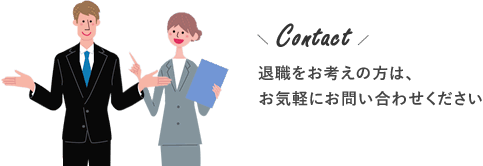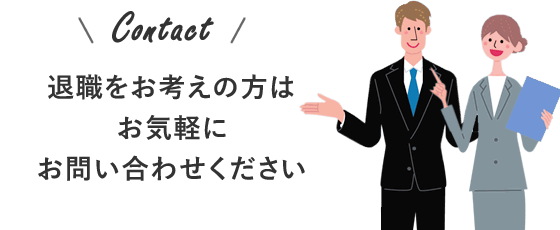2025.04.02
社会保険について
傷病手当金をもらって退職しても失業保険をもらうことはできる?
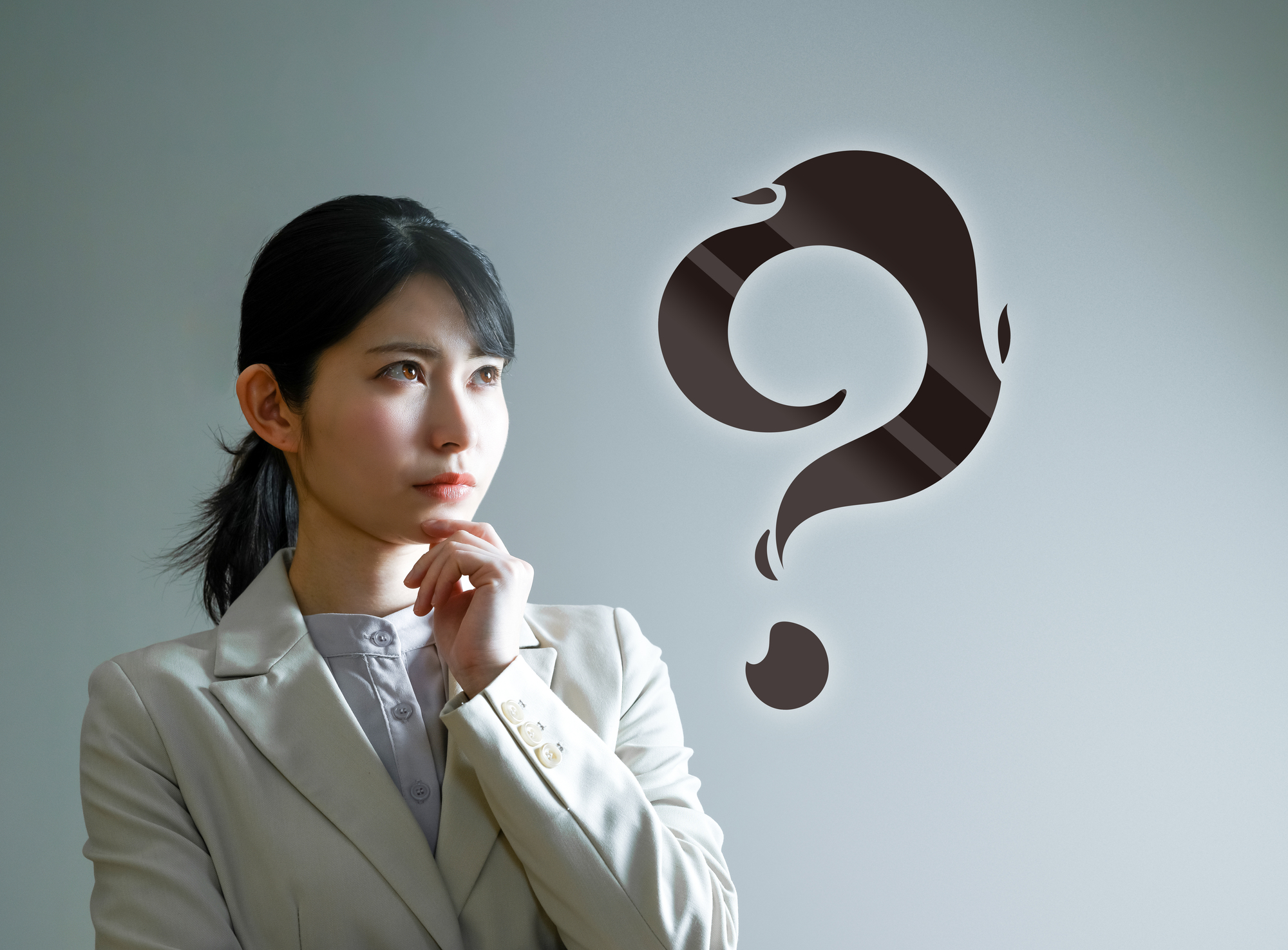
傷病手当金と失業保険は、どちらも退職後の生活を支える大切な制度です。しかし、原則的に同時受給はできません。本記事では傷病手当金と失業保険を効果的に活用する方法や、受給期間の延長手続き、注意点について詳しく解説します。制度を賢く利用して、安心して再就職活動に臨みましょう。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
傷病手当金と失業保険は同時にもらえない

傷病手当金と失業保険は、それぞれ目的が異なるため、同時に受給することはできません。傷病手当金は、病気やケガで働けない人に対して、収入の補填として支給される制度です。また失業保険は、働く意思を持ち求職活動をしている人が対象の制度です。
このように、それぞれ受給条件が異なるため、ルール上は同時に受け取ることが不可能です。しかし、受給するタイミングを工夫することで、両方の制度を活用することは可能です。以下では、その具体的な方法について詳しく解説します。
傷病手当金と失業保険を両方受給する方法
傷病手当金と失業保険は原則同時には受給できませんが、ポイントを理解することで両方の受け取りは可能です。効率的な受給方法を紹介します。
受給する時期を分ける
傷病手当金の支給が終わってから、失業保険を申請する方法です。この手順であれば、二重に受給することなく、両方の制度を活用できます。
退職後にすぐ働くことが難しい場合は、まずは傷病手当金を申請して受け取りましょう。支給期間は最長で1年6カ月あるため、その間は収入面での不安が軽減されます。傷病手当金の給付が終了したら、次に失業保険の手続きを行いましょう。ただし、退職後は早めにハローワークに行き「受給期間延長」の申請手続きを済ませておく必要があります。
失業保険の受給期間を延長する
退職後すぐに求職活動ができない場合は、失業保険の受給期間を最大4年間まで延長できます。 傷病手当金を受給している間に、ハローワークで延長手続きを行います。受給期間延長の手続きは、退職後、30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降に手続きを進める必要があります。
延長の手続きをすることで、まず治療に専念したうえで、その後に失業保険を受給しながら再就職活動が可能です。手続きをせず放置してしまうと、所定の期間を過ぎた時点で失業保険は受給できなくなります。
失業保険の受給期間を延長する方法
失業保険は、通常の受給期間を超えて延長できます。特に、病気やケガ、妊娠・出産、親族の介護などを理由に求職活動が難しい場合は、延長手続きを進めることで最大4年間まで受給期間を伸ばすことが可能です。ここでは、延長の条件や手続き方法について詳しく解説します。
延長できる主な条件
受給期間の延長が認められる主な条件には、以下のようなものがあります。該当する場合は、速やかに延長手続きを行いましょう。
病気やケガ
病気やケガによって入院や治療が必要な際、求職活動が難しいと判断されれば受給期間の延長が認められます。その場合、延長の理由を証明するために、医師の診断書や入院証明書などの書類が必要です。
妊娠や出産
妊娠中や産後で、すぐに働けない場合も延長の対象です。 出産予定日や産後の休養期間を証明できる母子手帳や医師の証明書を提出します。
親族の介護
要介護状態の同居している親族がいる場合、介護のために求職活動ができないと認められれば延長が可能です。その場合、介護認定証や介護保険証など、介護の必要性を証明する書類が必要です。
延長の手順
失業保険の受給期間の延長手続きは、ハローワークで行います。直接来所する場合と郵送で申請する場合の手順について説明します。
直接ハローワークに来所する場合
以下の手順で手続きを行います。
- ハローワーク窓口で受給期間延長申請書を受け取る
- 必要書類(離職票や理由を証明する書類※診断書や介護認定証など)を用意する
- 必要書類を管轄のハローワークへ持参して提出する
ハローワークに郵送する場合
最寄りのハローワークが遠いなど来所が難しい場合は、郵送での手続きも可能です。以下の手順で申請を行います。
- 受給期間延長申請書(ハローワークのWebサイトからダウンロード可能)を受け取る
- ハローワークの「雇用保険給付・教育訓練給付窓口」へ電話し、事前に郵送の旨を伝える
- 必要書類を郵送で提出する
郵送で提出する前に、書類をコピーします。コピーは手元に残しておきましょう。簡易書留やレターパックライトなど、追跡可能な方法で送ると安心です。
定年などが理由の場合
定年退職などが理由で受給期間を延長する場合、申請は退職日の翌日から2カ月以内に行う必要があります。もともとの受給期間である1年に加えて、最長で1年間の延長が可能です。以下の必要書類を持参し、原則として本人がハローワークに直接申請を提出しなければなりません。
- 受給期間延長等申請書
- 離職票-2
- 本人の印鑑(認印・スタンプ印以外)
失業給付の受給期間延長に必要な書類
失業保険の受給期間を延長するには、状況に応じて必要な書類が異なります。以下では、受給手続きが済んでいる場合と済んでいない場合の書類についてそれぞれ説明します。
受給手続きが済んでいる場合
受給手続きが済んでいる場合、以下の書類が必要です。
雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)
受給期間延長申請書および延長の理由を証明する書類(医師の証明書や介護認定証など)
受給手続きが済んでいない場合
受給手続きが済んでいない場合、以下の書類が必要です。
- (複数の離職票がある場合)お持ちのすべての離職票-2
- 受給期間延長申請書
- 延長の理由を証明する書類(例: 医師の証明書や介護認定証など)
傷病手当金から失業保険に切り替えるタイミング
傷病手当金と失業保険は、それぞれ受給条件が異なるため、切り替えのタイミングが重要です。特に、退職後すぐに働けるかどうかで対応が変わります。ここでは、退職後の状況に応じた切り替えのタイミングについて解説します。
退職後29日以内に働ける場合
退職後すぐに働ける場合は、傷病手当金の受給は終了し、速やかに失業保険の申請を行います。働ける状態になった時点で、傷病手当金は受給できません。
退職後、ハローワークで失業保険の手続きを行いましょう。自己都合退職の場合、2か月間の給付制限があるため、すぐに収入が途絶える点に注意が必要です。失業保険の給付開始をできるだけ早めるためにも、退職後すぐに手続きを行いましょう。
退職後30日以上、働けない場合
退職後30日以上働けない場合は、傷病手当金を優先して受給し、失業保険の受給は後回しにします。 最大1年6か月間、傷病手当金が受給可能です。
ハローワークで「受給期間延長」の手続きを行い、回復後に失業保険を申請しましょう。 傷病手当金の支給終了後、求職活動を開始すれば、失業保険の受給資格を得られます。
そもそも傷病手当金とは
傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなった際に、収入の一部を補填するための制度です。会社の健康保険に加入している人が対象で、条件を満たせば退職後も受給できます。ここでは、傷病手当金の受給条件や受給金額について詳しく解説します。
傷病手当金の受給条件
傷病手当金を受給するためには、以下の4つの条件を満たす必要があります。
1.業務外の病気やケガで療養中であること
業務上や通勤途中の病気やケガは労働災害保険の対象です。美容整形手術など、健康保険の対象外の治療は除外されます。
2.療養のため労務不能であること
労務不能とは、これまで従事していた業務ができない状態を指します。医師の意見や業務内容を考慮して判断されます。
3.4日以上仕事を休んでいること
療養開始から連続した3日間(待機期間)を除き、4日目から支給対象となります。土日や祝日も待機期間に含まれます。
4.給与の支払いがないこと
給与が一部支給されている場合は、傷病手当金から減額されます。会社から見舞金などが支給されている場合も、対象外となる可能性があるため注意しましょう。
傷病手当金の受給金額
傷病手当金の1日当たりの支給額は、以下の計算式で決まります。
「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2」
例えば、標準報酬月額が30万円の場合、1日当たり約6,600円が支給されます。
傷病手当金の受給期間
病気やケガで休んだ期間のうち、最初の3日間を除いた4日目から支給が開始されます。
受給期間は、手当の支給日数が合計で1年6か月になるまでです。
退職後に健康保険の資格を喪失した場合も、加入期間が継続して1年以上ある場合は受給できる可能性があります ただし、会社が加入している健康保険組合によっては、ルールが異なるため、事前に専門家に確認しましょう。
傷病手当金の申請方法
傷病手当金を申請する際の手順は以下のとおりです。
1.「健康保険傷病手当金支給申請書」を用意して記入
申請書は健康保険組合や協会けんぽのウェブサイトでダウンロード可能です。
2.勤務先と医療機関に必要な項目を記載してもらう
勤務先には賃金支払い状況、医療機関には病状や治療内容を記載してもらいます。
3.必要書類を揃え、健康保険組合もしくは協会けんぽに提出する
提出後、審査を経て支給が決定されます。通常、支給までに2〜3週間ほどかかります。
そもそも失業保険とは
失業保険(失業手当)は、働く意欲があり、いつでも就労できる状態の求職者に対して給付を行う雇用保険の制度です。ここでは、失業保険の概要や受給条件、申請方法について詳しく解説します。
失業保険の概要
失業給付は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になった場合に支給され、生活および雇用の安定を図るための制度です。 雇用保険(失業保険)に加入していることで、失業時に給付が受けられます。ただし受給には、一定の条件を満たしている必要があります。
失業保険の受給条件
失業手当を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
- 離職前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(特定受給資格者の場合は1年間に6カ月以上)
- 就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること
給付額は失業前の給与額と年齢によって変動する点、給付開始までの期間は会社都合や自己都合などの退職理由によって異なる点に注意が必要です。
失業保険の受給金額
失業手当の受給額は、「給付日数 × 基本手当日額」で決まります。一般的に、受給額は離職前の賃金の5〜8割程度です。
計算手順
- 賃金日額の計算方法: 退職前6カ月の賃金合計 ÷ 180
- 基本手当日額の計算方法: 賃金日額 × 給付率(50~80%)
- 基本手当総額の計算方法: 基本手当日額 × 給付日数
退職前6カ月の賃金合計には、ボーナスは含まれません。給付率は、離職時の年齢や退職前の賃金により異なり、賃金が低いほど給付率が高くなります。
失業保険の受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。 所定給付日数が330日の場合は1年と30日、360日の場合は1年と60日となります。ただし病気、けが、妊娠、出産、育児などで30日以上働けない場合、働けない期間分(最長3年)だけ受給期間を延長可能です。
失業保険の申請方法
ここからは失業保険の申請方法について、必要書類や具体的な手続きを解説します。
必要書類を揃える
ハローワークに来所する前に、必要書類を準備しておくと手続きがスムーズです。失業保険の申請には、以下の書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票-1・2
- 雇用保険被保険者証
- 証明写真(たて3cm×よこ2.4cm、正面上半身)×2
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 住所・氏名・年齢が確認できる本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1つ)
ハローワークで求職を申し込む
退職後は、ハローワークで求職の申し込みを行います。具体的な流れは以下のとおりです。
- 求職申込書に記入する
- 必要書類の提出、職業相談を行う
- 雇用保険説明会の日時が決定する
離職票の提出と求職の申し込みは必須です。申し込み後、受給資格が決定すると「失業等給付受給資格者のしおり」が渡されます。雇用保険説明会は申請日から7日後以降に案内されるため、忘れずにメモしておきましょう。
待機期間を過ごす
ハローワークで受給資格を得ると、7日間の待機期間が設けられます。 待機期間中、失業保険は支給されません。 短時間勤務やアルバイトも就労とみなされるため、待機期間中は就労を避けましょう。
待機期間中に入社日を迎えた場合、再就職手当も受給できません。待機期間中は、就労・入社を控え、この期間が過ぎることを待ちましょう。
雇用保険説明会に参加する
求職の申し込み時に案内された雇用保険受給説明会に参加します。説明会では失業保険の仕組みや受給の流れ、求職方法などが詳しく説明されます。疑問点があれば、その場で解決しておきましょう。
説明会の持ち物は以下のとおりです。
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 印鑑
- 筆記用具
説明会終了後、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡され、初回の失業認定日が案内されます。
失業認定日にハローワークを訪れる
失業認定日とは、ハローワークが失業の事実を認定する日です。指定時間に来所し失業認定申告書を提出して就職活動の実績を報告します。
通常の失業認定日は4週間ごとに1日ですが、初回の失業認定日は、離職票を提出した日から約3週間後に設定されます。失業認定日に来所しなかった場合、失業認定が受けられず、基本手当が支給されないため、必ずスケジュールを管理しましょう。
傷病手当金と失業保険を両方受給する際の注意点
傷病手当金と失業保険は、受給条件が異なるため、両方を受給する場合は細かな条件に注意する必要があります。特に、退職日までの手続きや通院のタイミングが重要です。ここでは、両方を受給する際の注意点について詳しく解説します。
退職日を迎える前に連続3日以上の休みを取る
傷病手当金を受給するためには、連続3日以上の休暇が条件です。 3日間の連続休暇は、土日祝日や有給休暇、大型連休(正月休みやゴールデンウィークなど)を利用しても問題ありません。 あらかじめ退職のタイミングを調整し、効率良く休みを取得しましょう。
ただし、共済組合に加入している場合は、公休を除いた3日間の連続した休暇が必要です。退職日前に3日以上の連続休暇を取得し、条件を満たしておきましょう。
3連休の前日までに初診を受ける
傷病手当金を受給するには、3連休の前日までに初診を受ける必要があります。 診断書は必須ではありませんが、条件のカウントには初診日が重要です。
ただし、職場のストレスが原因とみなされた場合、労災と判断され傷病手当金の対象外になる可能性があります。「原因は不明」としておくと無難です。労務不能と診断されなかった場合は、別の心療内科などの受診も検討しましょう。
退職日当日に出社しない
退職日当日に出社してしまうと、傷病手当金の対象外になる可能性があります。 病院で「働けない証明」をもらったら、退職日当日の出社は控えましょう。
退職日前日までに引き継ぎや備品の返却を済ませておくと安心です。 退職日までに3連休を取得した場合は、その翌日が傷病手当金の支給対象となります。
毎月1度病院に通う
給付金の受給中は、毎月1度は病院に通う必要があります。 継続的な通院がない場合、治療への積極性が見られないと判断され、受給資格を失う可能性がある点に注意が必要です。
毎月の給付金申請時には、自分と医師が記入した申請書を健康保険組合に提出します。給付金の停止を避けるためにも、継続的に通院しましょう。
定期的に求職活動を行う
4週間ごとの認定日には、求職活動の実績報告が必要です。応募や面接だけでなく、職業相談やセミナーの受講、転職フェアへの参加なども実績にカウントされるため、情報収集に努めましょう。
活動実績が不足すると、失業保険の支給が停止される可能性があることから、定期的な求職活動が必要です。
そもそも傷病手当金がもらえない・調整されるケース
傷病手当金はすべてのケースで受給できるわけではありません。特に、他の給付金や給与がある場合は調整が行われ、支給されないことがあります。ここでは、傷病手当金がもらえない、または調整されるケースについて解説します。
給与を受け取っている
傷病手当金は、「給与を受け取れない人の補助」を目的とした制度です。Wワーク等で給与が支給されている場合は、傷病手当金は支給されません。 ただし、給与の日額が傷病手当金の日額を下回る場合は、その差額が支給されます。
障害厚生年金・障害手当金などを受給している
すでに障害厚生年金や障害手当金を受給している場合、その病気やケガを理由とした傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の日額が傷病手当金の日額を下回る場合は、差額が支給されます。
また障害手当金が傷病手当金の総額に達した場合、その後は傷病手当金が支給されます。
労災保険から休業補償給付を受給している
労災保険は、業務上のケガや病気が対象のため、傷病手当金との併給はできません。仮に業務外の病気やケガにより仕事を休んでいても労災保険から休業補償給付を受給している場合も同様です。
ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額を下回る場合は、差額が「傷病手当金」として支給されます。
老齢退職年金を受給している
退職後も傷病手当金を受けていた人が老齢退職年金を受給すると、原則として支給が停止されます。年金と傷病手当金の二重取りを防ぐため、一定の調整が行われるためです。
ただし、老齢退職年金の日額が傷病手当金の日額を下回る場合は、差額が支給されます。
出産手当金を受給している
出産手当金は、女性が出産を理由として仕事を休んでいる期間かつ給料が支払われない場合の制度です。傷病手当金と出産手当金の期間が重なった場合は、出産手当金が優先され、傷病手当金は支給されません。
ただし、傷病手当金の日額が出産手当金の日額を上回る場合は、差額が支給されます。
傷病手当金や失業保険がもらえない場合の選択肢

傷病手当金や失業保険が受給できない場合も、他の支援制度が利用できる可能性があります。職業訓練や生活費の支援、障害年金などを活用し、再就職や生活再建のサポートを受けるために、それぞれの制度について詳しく解説します。
求職者支援制度
求職者支援制度は、失業保険の受給資格がない求職者や、受給期間が終了した人を対象にした支援制度です。 職業訓練と生活費の支援を行い、再就職に必要なスキルを身につけることを目的としています。
訓練中の生活費支援となる「職業訓練受講手当」、通学費用の補助となる「通所手当」、遠方からの通学者向けの宿泊費補助「寄宿手当」の3つがあります。条件を満たせば、無償で職業訓練を受けられるため、失業保険が受給できない場合の有力な選択肢です。
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は、収入の減少や失業により生活資金が不足した場合に利用できる制度です。実施元は、各都道府県の社会福祉協議会で低金利または無利子での貸し付けが可能です。
返済期間も長期にわたり設定されているため、負担が少なく、生活再建のための資金や、就職活動に必要な費用なども貸付対象です。また、連帯保証人がいれば、無利子で借り入れできます。
障害年金
ストレスによる体調不良が長期化し、日常生活や労働に支障をきたす場合は、障害年金の対象になる可能性があります。 障害年金とは、国民年金や厚生年金の被保険者が一定の障害状態になったときに支給される年金です。
初診日において年金保険料の納付要件を満たしていることや、障害認定日において所定の障害等級に該当していることなどの受給条件をクリアする必要があります。うつ病や適応障害などストレス性の疾患も障害年金の対象になる可能性があるため、検討してみましょう。
傷病手当金と失業保険を両方もらう際のよくある質問
傷病手当金と失業保険は、受給条件やタイミングが異なるため、両方を受け取る際に疑問を持つ方も少なくありません。ここでは、よくある質問に答えながら、制度の仕組みを解説します。
傷病手当金と失業保険はどちらがお得ですか?
傷病手当金は給与の2/3が支給され、最長1年6か月間受け取れます。 失業保険は、退職理由や年齢、雇用期間によって給付日数や金額が変わります。どちらがお得かは状況や条件によって異なるため、「社会保険給付金サポート」の専門家に相談し最適な選択を検討することをおすすめします。
失業保険はすぐに受け取れますか?
自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加えて、2カ月(2025年4月より1カ月)の給付制限があり、すぐに受給できません。
ただし、会社都合退職の場合は、待機期間7日後に受給が開始されます。 さらに退職後、傷病手当金を30日以上受給している場合は、給付制限は免除されます。 条件を満たしていれば、退職後すぐに失業保険の支給を受けられる可能性があります。
傷病手当金とはなんですか?
傷病手当金とは、業務外の病気やケガで働けなくなった際に、収入の補填として支給される給付金です。対象は、健康保険に加入している被保険者かつ下記4つの条件を満たす方が受給できます。
- 業務外の病気やケガで療養中
- 療養のため労務不能
- 4日以上仕事を休んでいる
- 給与の支払いがない
まとめ
傷病手当金や失業保険は、退職後の生活を支える重要な制度ですが、それぞれ受給条件が異なるため、両方を受け取りたい場合は工夫が必要です。もし、いずれの制度も受給できない場合は、求職者支援制度や生活福祉資金貸付制度、障害年金といった選択肢を検討しましょう。
失業保険の受給条件や傷病手当金の申請方法に不安がある方は、「社会保険給付金サポート」の利用もおすすめです。専門家のアドバイスを受けて、最適な支援制度を選びましょう。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
おすすめの関連記事
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 新型コロナウイルスについて
- 社会保険について
- 退職代行について
- 税金について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
障害年金を知ろう
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは必須?スムーズな業務引き継ぎのポイント
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
テーマ
- クレジットカード
- 資格取得
- 退職願
- 職業訓練受講手当
- 自己PR
- 社会保険給付金
- 退職代行
- アルバイト
- 精神疾患
- 退職届
- インフルエンザ
- 確定申告
- 職業訓練受講給付金
- 退職代行サービス
- 雇用保険
- うつ病
- 面接
- 感染症
- 保険料
- 退職給付金
- ブラック企業
- 健康保険
- 統合失調症
- 障害手当金
- 引っ越し
- 社会保障
- ハローワーク
- ハラスメント
- 年金
- 契約社員
- 自己都合
- 社宅
- 就職
- 就業手当
- パワハラ
- 転職活動
- 弁護士
- 会社都合
- 障害者手帳
- 労働基準法
- 傷病手当
- モラハラ
- 転職サイト
- 公的貸付制度
- 失業給付
- 精神保険福祉手帳
- 雇用契約
- 退職コンシェルジュ
- セクハラ
- 職務経歴書
- 生活福祉資金貸付制度
- 新型コロナウイルス
- 労災
- 内定
- 社会保険給付金サポート
- 障害年金
- 人間関係
- 通勤定期券
- 有給消化
- 産休
- 就労移行支援
- 雇用保険サポート
- 引き継ぎ
- スタートアップ
- 不支給
- 休職
- 育児休暇
- 業務委託
- 退職手当
- 給与
- 転職
- 等級
- 免除申請
- 解雇
- 社会保険
- 残業代
- 違法派遣
- 離職票
- 適応障害
- 大企業
- 福利厚生
- 退職金
- 派遣契約
- 労務不能
- 住宅確保給付
- 中小企業
- 失業手当
- 会社都合退職
- 障害厚生年金
- 傷病手当金
- 給付金
- ベンチャー企業
- 就職困難者
- 自己都合退職
- 失業保険
- 年末調整
- 職業訓練
- 会社倒産
- 再就職手当
- 退職
- ブランク期間
- 障害者控除
- 再就職
- 退職勧奨
- 転職エージェント
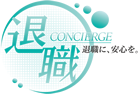




 サービス詳細
サービス詳細