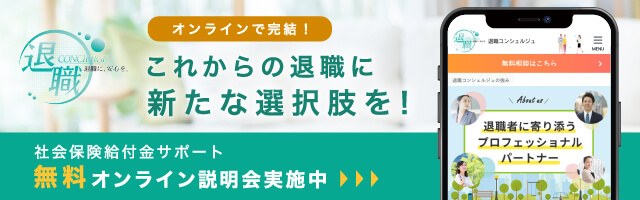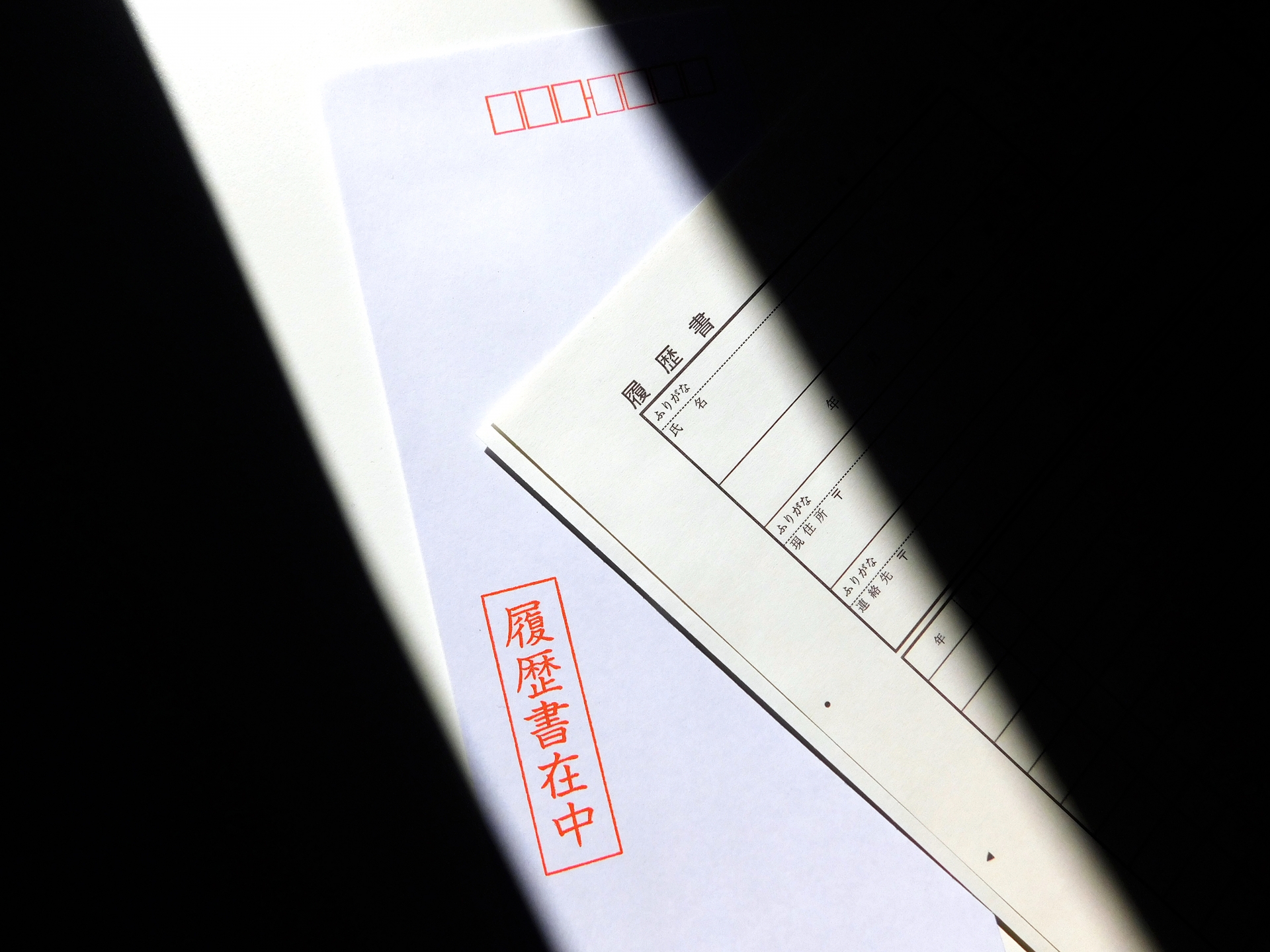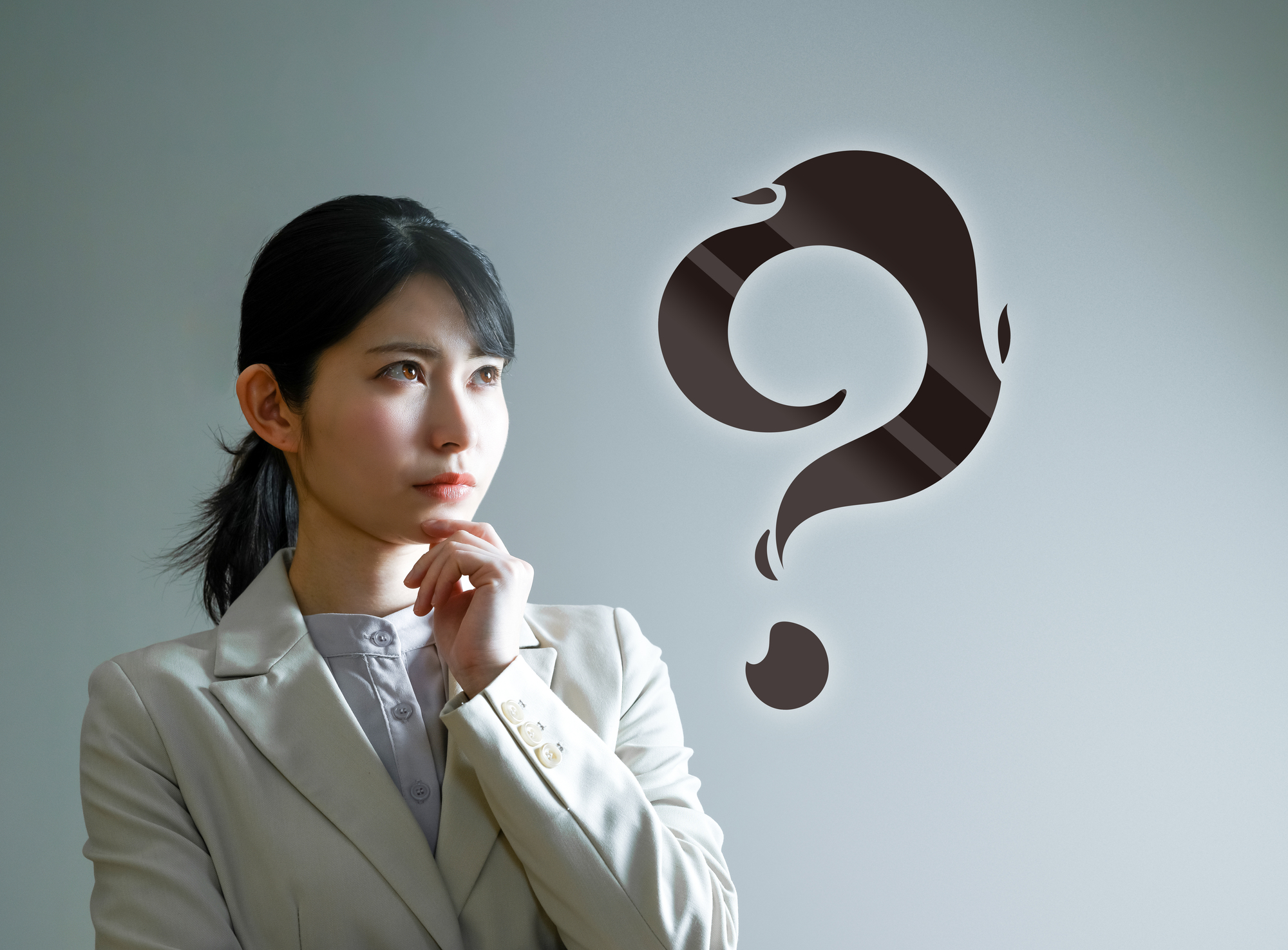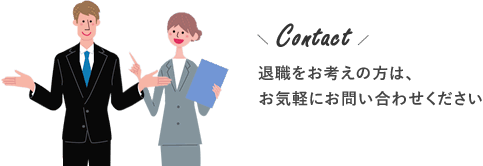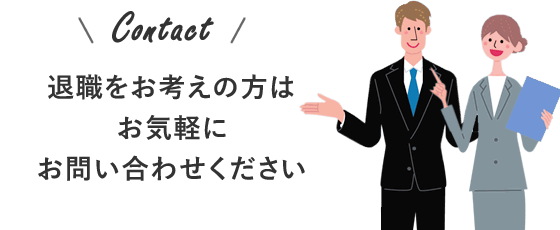2025.03.31
退職について
失業保険をもらうデメリットとは?もらわないほうが良いケースも紹介

失業保険は退職後にもらうことができる手当ですが、雇用保険の加入期間がリセットされるなどのデメリットがあります。また、退職理由によって失業保険をもらうことでデメリットが生じる可能性もあるため、慎重に検討しなければなりません。
本記事では、失業保険をもらうことで生じるデメリットと退職理由ごとのデメリット、注意点を解説します。失業保険を受け取るメリットやもらわないほうが良いケース、そもそも受け取れない人の具体例や失業保険の概要、受給手続きなどもご紹介しますのでぜひ参考にしてください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
失業保険のデメリットは雇用保険の加入期間がリセットされること

失業保険をもらうデメリットは、受給することで雇用保険の被保険者期間がリセットされる点です。一度失業保険を受給した後に、再度受給するためには、再就職後に一定の加入期間を満たさなければなりません。
そのため、再就職後に短期間で再び離職した場合は必要な加入期間を満たせず、失業保険を受給できない可能性があります。失業保険の受給を検討する際には、将来的なリスクも考慮することが重要です。
自己都合退職で失業保険を受け取るデメリット
自己都合退職で失業保険を受け取るデメリットは、次の3つです。
- 失業保険がすぐにもらえない
- 給付日数が少ない
- 総支給額が少ない
失業保険がすぐにもらえない
失業保険を受給するには、退職後に「ハローワークへ離職票を提出した日」から7日間の待機期間を待たなければなりません。自己都合退職の場合は、待機期間終了後に2ヵ月間(※2025年4月以降は1ヵ月間)の給付制限期間が発生します。
自己都合退職に伴う給付制限期間は、2020年10月1日以降に変更され、原則として待機期間後に2ヵ月となりました。ただし、過去5年間で自己都合退職が3回以上ある場合は、3ヵ月に延長されます。
重大な過失による解雇(重責解雇)の場合も、3ヵ月間の給付制限が適用されます。さらに、ハローワークから紹介された仕事や指示された職業訓練を拒否した場合は、拒否した日から1ヵ月間の給付制限が課される点にも注意が必要です。
給付日数が少ない
自己都合退職の場合、会社都合退職に比べてそもそもの給付日数が少ない点にも注意が必要です。特定受給資格者や一部の特定理由離職者に該当する場合、失業保険の給付日数は最大で330日、就職が困難な人の場合は最大で360日となります。
しかし、自己都合退職など、上記以外の給付日数は最大で150日となるため、全体的に受け取れる期間が短くなる点に留意しましょう。
総支給額が少ない
自己都合退職の場合、会社都合退職に比べて総支給額が少なくなる点もデメリットの1つです。失業保険の総支給額は、以下の計算式で求められます。
「1日あたりの失業保険の金額(基本手当日額)」×「給付日数(所定給付日数)」
1日あたりの支給額(基本手当日額)は、自己都合・会社都合に関係なく同じですが、給付日数に差があります。自己都合退職の場合、最大給付日数は150日であるのに対し、会社都合退職の場合は最大で330日(就職困難者は最大360日)です。
会社都合退職で失業保険を受け取るデメリット
会社都合退職で失業保険を受け取ること自体には、上述したような「雇用保険の加入期間がリセットされること」以外に目立ったデメリットはありません。
ただし、会社都合退職になるということに関しては、次のデメリットがあります。
再就職活動で不利になる可能性がある
会社都合退職の場合、再就職活動の際に不利になる可能性があります。転職活動では、採用担当者が退職理由について質問するケースがあるためです。
解雇理由が個人の能力不足や勤務態度にあると判断された場合、採用側に与える印象は良くないでしょう。
自分の希望するタイミングでの退職が難しい場合がある
会社都合退職には、自分の希望するタイミングで退職できないというデメリットがあります。突然の解雇やリストラが行われると、退職時期を計画的に決めることが困難です。結果として、キャリアプランや生活設計が大きく崩れかねません。
再就職活動においても、急な退職だった場合、応募先の企業から退職理由について詳しく尋ねられる可能性があります。さらに、離職期間が長引くと経済的な不安が生じ、焦って自分に合わない職場を選んでしまうケースも考えられるでしょう。
失業保険におけるその他のデメリット(注意点)
失業保険を受け取る際は上記以外にも、次のデメリットがあります。
- 自己都合と会社都合で受給額や要件が異なる
- 申請手続きに時間がかかる
- 受給中でも健康保険や年金の支払いがある
- 月2回の求職活動や失業認定を受ける必要がある
- アルバイトに制限がある
失業保険の制度を最大限利用するためにも、それぞれのデメリットを理解しておきましょう。
自己都合と会社都合で受給額や要件が異なる
自己都合退職と会社都合退職では、失業保険の給付制限期間が異なります。自己都合で退職した場合、失業保険を受け取れるようになるまでに、約2ヵ月と1週間かかる点に注意が必要です。一方、会社都合退職の場合は、7日間の待機期間が終わるとすぐに給付が開始されます。
受給資格に必要な雇用保険の被保険者期間も異なります。自己都合退職の場合、離職前の2年間で通算12ヵ月以上の被保険者期間が必要です。会社都合退職の場合は、離職前の1年間で通算6ヵ月以上の被保険者期間があれば受給資格を得られます。
申請手続きに時間がかかる
失業保険は受給開始までに時間がかかることや、手続きの煩雑さを感じやすい点もデメリットです。例えば、離職票、マイナンバーカード、本人確認書類、写真、預金通帳など、多くの書類を準備しなければなりません。
一人で手続きをするのは大変だと感じる場合は、ぜひ「社会保険給付金サポート」をご活用ください。専門家が申請手続きを丁寧にサポートいたします。サポートのご利用前には担当コンシェルジュによる無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
受給中でも健康保険や年金の支払いがある
失業保険を受給している間も、健康保険料や年金保険料の支払い義務は継続します。これまで会社が半分負担していた分も、自分で全額支払う必要があるため注意が必要です。年金については、厚生年金から国民年金第1号被保険者へ種別変更の手続きを行わなければなりません。
保険料の支払いが難しい場合、国民年金保険料の免除や納付猶予制度を利用できますが、申請が必要です。手続きを怠ると未納扱いとなり、将来の年金受給額に影響を及ぼす可能性があります。失業中の経済的負担を軽減するためにも、免除制度や猶予措置を活用し、早めに対応することが大切です。
月2回の求職活動や失業認定を受ける必要がある
失業保険の受給には、定期的な求職活動と失業認定が必須です。具体的には、4週間に1度ハローワークで失業認定を受ける必要があり、原則として2回以上の求職活動実績を報告しなければなりません。
求職活動は、企業への応募だけでなく、ハローワーク主催のセミナー参加も含まれます。計画的に行わないと、認定が受けられず、失業保険の支給が遅れる、または停止される可能性があるため注意しましょう。
アルバイトに制限がある
失業保険受給中のアルバイトには、いくつかの制限があります。まず、待機期間中は、いかなるアルバイトもできません。
待機期間終了後はアルバイトが可能ですが、労働時間や収入によっては、失業保険の減額や支給停止に繋がります。また、アルバイトによっては就職したとみなされ、失業保険の受給資格を失う場合もあります。
失業保険を受け取るメリット
失業保険をもらうことはデメリットばかりではありません。例えば、次の3つのようなメリットがあげられます。
- 生活費を補填できる
- 焦らず自分に合った職場をじっくり探せる
- 「再就職手当」を受け取れる
失業保険を受け取るかどうかは、メリットデメリットを比較して検討することが大切です。
生活費を補填できる
失業保険は、失業中の生活を支える重要なセーフティーネットです。家賃、食費、公共料金など、日々の生活に必要な費用を補填することで、経済的な不安を軽減します。
受給額は、離職前の給与の約5割から8割程度であり、一定の生活水準を維持することが可能です。
焦らず自分に合った職場をじっくり探せる
失業保険があると、経済的なプレッシャーが軽減し、焦らずじっくりと職場を探すことができます。また、ハローワークの職業訓練やセミナーに参加し、スキルアップを図ることも可能です。
このような機会を積極的に活用することで、自身の市場価値を高め、より良い条件での再就職を目指せます。短期間での再離職を防ぎ、長期的なキャリア形成に役立つでしょう。
「再就職手当」を受け取れる
失業保険の受給中に早期に再就職が決定した場合、「再就職手当」を受け取ることができます。再就職手当は早期の再就職を促進するための制度です。再就職手当の金額は、基本手当日額×支給残日数基本手当日額の残りの支給日数の60%または70%です。
早期に再就職できると、スムーズな社会復帰が可能になります。このように再就職手当は、積極的な再就職活動を支援するための制度です。
失業保険をもらわないほうがいい人
失業保険は、失業後の生活を安定させて再就職の機会を図る人にとって重要な収入源となります。
ただし、次に説明するように失業保険をもらわないほうがいい人もいるため、注意が必要です。
転職先がすでに決まっている
転職先がすでに決まっている場合は、失業保険をもらわない方が有利になることがあります。失業保険を受け取ると雇用保険の加入期間がリセットされるため、被保険者期間が10年〜20年以上の方や、あと1年で給付日数が増える方は、失業保険を利用しない方が得になる場合が起こりうるからです。
失業保険の給付日数は離職理由に応じて変わるため、失業後すぐに就職して以前からの被保険者期間を引き継ぐ方が得になるケースに注意しましょう。
しばらく働くことができない
失業後のしばらくの期間に働くことができない場合は、失業保険はもらうべきではありません。失業保険は再就職を支援する制度であり、空白期間が長くなると転職に悪影響があるため、受給中は早期就職を目指すべきだからです。
ただし、妊娠・育児・介護などが理由で働けない場合は、延長手続きを行うことで最大4年まで受給期間を延ばせます。
そもそも失業保険がもらえない人
失業保険を受給するには、いくつか条件を満たす必要があります。以下の条件に該当する人はそもそも失業保険がもらえないため、事前に確認しましょう。
再就職する意思や能力がない
再就職する意思がない場合は、失業保険の受給要件を満たしていないと判断される可能性が高くなります。失業保険の給付要件には「積極的に就職しようとする意思」が求められ、退職後にしばらく休むつもりや留学を計画している場合は給付が難しくなる可能性があるためです。
また、定期的に失業保険を受給するには、定期的に求職活動を行い4週間に一度の失業認定を受ける必要があります。就職の意思があっても積極的な就職活動をしていない場合は、失業認定を受けられず、失業保険が受給できない可能性が高くなります。
雇用保険の加入期間を満たしていない
雇用保険の加入期間を満たしていない場合も失業保険をもらえません。過去の雇用保険の加入期間も失業保険の受給要件に含まれ、離職前の2年間に12ヵ月以上の雇用保険加入期間が必要だからです。そのため、12ヵ月未満の自己都合退職では受給できない点に注意が必要です。
なお、倒産や解雇などのやむを得ない事情がある場合、被保険者期間が1年間で6ヵ月以上あれば要件が緩和されて失業保険を受給することができます。
また、病気や妊娠などで30日以上賃金を受け取れなかった場合は、休職した期間分、算定対象期間が延長されるため、受給資格を満たす可能性があります。その休職期間が被保険者期間に加算され、さらに受給資格を満たす可能性があります。
ハローワークで認定手続きを行っていない
失業保険を受給するには、4週間に一度ハローワークで失業認定手続きを行う必要があります。失業認定が必要な日は、求職申し込みをした際に指定され、「失業認定申告書」に求職活動状況を記載し、「雇用保険受給資格者証」とともにハローワークに提出しなければなりません。
認定手続きを行わないと失業保険は支給されないため、必ず4週間に一度手続きを行うことが重要です。
一定の収入がある
一定の収入がある場合は、失業状態とみなされず失業保険がもらえない可能性があります。
失業保険が認定された場合、前述した4週間に一度の認定手続き時に、副業で得た収入や働いた日の申請を行います。このとき、収入があるにもかかわらず申請を怠ると、受給停止や不正受給額の返還や3倍の納付が命じられる可能性があるため正確に申請するようにしましょう。
すでに年金を受給している
すでに年金を受給している人は、失業手当を受給できない可能性があります。具体的には、老齢厚生年金と失業手当は同時に受け取れません。
また、失業手当の受給期間は、老齢厚生年金や退職共済年金の支給が全額停止されますが、失業手当の受給内容に変更は生じません。
年金を受給予定の人は、失業手当と年金のどちらを受け取るほうがメリットがあるかを、金額をもとに比較して慎重に判断してください。
すでに傷病手当金を受給している
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった場合に一定額が支給される社会保険・健康保険の保障のことです。
傷病手当金は働けない人向け、失業手当は働く意思と能力がある人向けの保障であり、傷病手当金を受給している場合は失業保険の受給資格を満たさないため、傷病手当金と失業手当は同時に受け取ることができません。
そもそも失業保険とはどんな制度?
失業手当(失業保険)は、働く意欲がありいつでも就労できる状態の求職者へ給付を行う雇用保険の制度です。ここまでは失業保険をもらうメリットやデメリットなどを解説してきましたが、具体的にはどのような制度なのでしょうか。
ここでは、失業保険の受給要件と受給期間について解説します。
失業保険の受給条件
失業保険には受給条件があり、受給するには条件を満たさなければなりません。具体的な条件は次のとおりです。
- 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
- 離職前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(特定受給資格者の場合は1年間に6カ月以上)
- 就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること
なお、給付額は失業前の給与額と年齢によって変動します。
また、給付開始までの期間は退職理由によって異なり、会社都合の場合は7日間の待期期間が発生し、自己都合退職の場合は待機期間に加えて2ヵ月間(2025年4月以降は1ヵ月間)の給付制限期間が設けられます。
失業保険の受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年間(所定給付日数が330日の場合は1年と30日、360日の場合は1年と60日)です。
病気、けが、妊娠、出産等で30日以上働けない場合は、その期間分だけ受給期間を延長できますが、最長でも3年間の延長となります。
失業保険の受給金額
失業保険の受給金額は、「基本手当日額 × 給付日数」で決定します。一般的に、受給額は離職前の賃金の5〜8割程度に設定されています。ここからは、順を追って基本手当総額の計算方法を解説します。
賃金日額を計算する
まず、賃金日額を計算します。賃金日額とは、離職前の直近6ヵ月間に支払われた賃金の総額を180で割った金額のことです。
賃金には、基本給のほか、残業代や各種手当(通勤手当、住宅手当など)が含まれますが、賞与や退職金、祝い金などの臨時的な賃金は含まれないないので注意しましょう。
基本手当日額を計算する
続いて、基本手当日額を計算します。基本手当日額とは、賃金日額に給付率(50%〜80%)を掛け合わせたものです。
給付率は、賃金日額が低いほど高く設定されており、具体的な給付率は厚生労働省の基準に基づいて決定されます。
基本手当総額を計算する
最後に、基本手当総額を計算します。冒頭でお伝えした通り、基本手当日額に所定給付日数を掛け合わせることで、総受給額が算出されます。
所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢などによって異なるため、確認が必要です。例えば、自己都合退職の場合において、被保険者期間が1年以上5年未満であれば90日が所定給付日数となります。
具体的な例として、離職前6ヵ月間の賃金総額が180万円の場合、賃金日額は180万円÷180日=1万円です。仮に給付率が60%であるとすると、基本手当日額は1万円×60%=6,000円になり、所定給付日数が90日の場合、総受給額は6,000円×90日=54万円となります。
なお、基本手当日額には年齢ごとに上限額と下限額が設定されています。
失業保険の申請方法と受給までのステップ

ここからは、実際に失業保険を受けるための申請方法と受給までの流れを解説します。
必要書類を揃える
まず、ハローワークで求職申し込みをする前に必要書類を準備します。
必要な書類は次のとおりです。
- 雇用保険被保険者離職票-1・2
- 雇用保険被保険者証
- 証明写真(たて3cm×よこ2.4cm、正面上半身)×2
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 住所・氏名・年齢が確認できる本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1つ)
ハローワークで求職を申し込む
上記の書類がそろえば、ハローワークに持参して求職の申し込みを行います。ハローワークの窓口では、具体的には次の流れで進みます。
- 求職申込書に記入する
- 必要書類の提出、職業相談を行う
- 雇用保険説明会の日時が決定する
退職後も求職の意思があり失業保険を受けたい場合は、ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みが必要です。申し込み後、受給資格が決定すると「失業等給付受給資格者のしおり」が渡されます。
「雇用保険説明会」の日時案内は申請日から7日後以降になるため、伝えられた日程を忘れずにメモしておきましょう。
待機期間を過ごす
ハローワークで求職申し込みを行い受給資格を得ると、7日間の待機期間が設けられます。なお、求職申し込みをした日から失業期間が7日に満たない場合は失業保険は給付されないため注意が必要です。
この待機期間の7日間は、ハローワークが失業状況を調査する期間です。短時間の勤務やアルバイトも就労とみなされるため、一切の就労をしないことが求められます。
また、失業保険受給中に受給日数を残して再就職した場合には再就職手当が支給されますが、7日間の待期期間中に入社日を迎えると、再就職手当を受け取ることはできなくなります。再就職手当の受給を目指している場合は、求職活動や入社日の関係に注意が必要です。
雇用保険説明会に参加する
失業保険を受給するには、求職申込時に案内された雇用保険説明会に参加しなければなりません。雇用保険説明会では、失業保険の仕組みや受給の流れ、求職方法などが詳しく説明されるため、理解を深めましょう。
なお、雇用保険説明会への参加時は、以下の持ち物を持参してください。
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 印鑑
- 筆記用具
説明会の終了後に、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡されます。同時に初回の失業認定日が案内されるため、日程をメモしておきましょう。
失業認定日にハローワークを訪れる
雇用保険説明会で案内された失業認定日にハローワークを訪れます。
失業認定日とは、ハローワークが失業の事実を認定する日のことで、失業認定申告書を提出し、応募や面接などの就職活動の実績を報告しなければなりません。
初回の失業認定日は、離職票を提出した日から約3週間後に設定されます。それ以降、通常は4週間ごとに1日、ハローワークから指定された平日が失業認定日となります。
まとめ
退職後に失業保険をもらうにあたっては、それまで継続していた雇用保険の加入期間がリセットされてしまうデメリットがあります。また、求職の申し込み後7日間は待期期間となるため、失業保険を受け取ることができず、自己都合退職の場合はさらに給付制限期間が設けられるため注意が必要です。
失業保険は失業後の生活を安定させるために重要な手当ですが、手続きが煩雑で申請に時間がかかるなど、大変だと感じることもあるでしょう。
失業保険の申請手続きに不安を感じていたり困っている方は、ぜひ「社会保険給付金サポート」をご利用ください。経験豊富なプロのコンシェルジュが申請手続きをサポートいたしますので、スムーズに失業保険を受け取れます。無料のWeb説明会やLINEでの相談も承っていますので、お気軽にご利用ください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
おすすめの関連記事
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 新型コロナウイルスについて
- 社会保険について
- 退職代行について
- 税金について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
障害年金を知ろう
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは必須?スムーズな業務引き継ぎのポイント
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
テーマ
- クレジットカード
- 資格取得
- 退職願
- 職業訓練受講手当
- 自己PR
- 社会保険給付金
- 退職代行
- アルバイト
- 精神疾患
- 退職届
- インフルエンザ
- 確定申告
- 職業訓練受講給付金
- 退職代行サービス
- 雇用保険
- うつ病
- 面接
- 感染症
- 保険料
- 退職給付金
- ブラック企業
- 健康保険
- 統合失調症
- 障害手当金
- 引っ越し
- 社会保障
- ハローワーク
- ハラスメント
- 年金
- 契約社員
- 自己都合
- 社宅
- 就職
- 就業手当
- パワハラ
- 転職活動
- 弁護士
- 会社都合
- 障害者手帳
- 労働基準法
- 傷病手当
- モラハラ
- 転職サイト
- 公的貸付制度
- 失業給付
- 精神保険福祉手帳
- 雇用契約
- 退職コンシェルジュ
- セクハラ
- 職務経歴書
- 生活福祉資金貸付制度
- 新型コロナウイルス
- 労災
- 内定
- 社会保険給付金サポート
- 障害年金
- 人間関係
- 通勤定期券
- 有給消化
- 産休
- 就労移行支援
- 雇用保険サポート
- 引き継ぎ
- スタートアップ
- 不支給
- 休職
- 育児休暇
- 業務委託
- 退職手当
- 給与
- 転職
- 等級
- 免除申請
- 解雇
- 社会保険
- 残業代
- 違法派遣
- 離職票
- 適応障害
- 大企業
- 福利厚生
- 退職金
- 派遣契約
- 労務不能
- 住宅確保給付
- 中小企業
- 失業手当
- 会社都合退職
- 障害厚生年金
- 傷病手当金
- 給付金
- ベンチャー企業
- 就職困難者
- 自己都合退職
- 失業保険
- 年末調整
- 職業訓練
- 会社倒産
- 再就職手当
- 退職
- ブランク期間
- 障害者控除
- 再就職
- 退職勧奨
- 転職エージェント
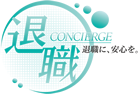




 サービス詳細
サービス詳細