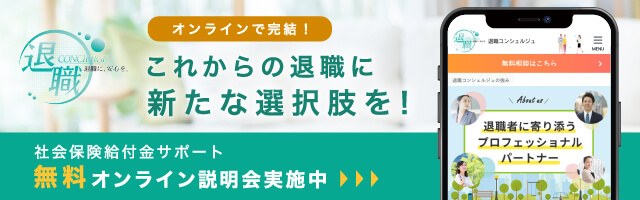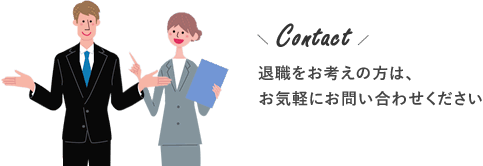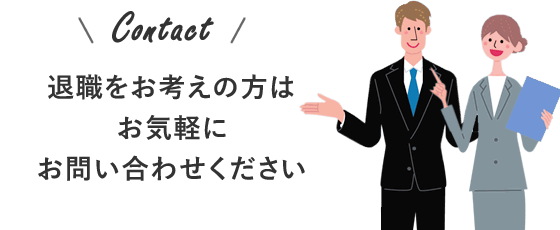2025.04.03
転職・再就職について
失業保険は何回もらえる?もらうデメリットや注意点も解説

失業保険は、失業中の生活を支える重要な制度です。しかし、受給には条件や手続き、デメリットもあるため、正しく理解しておくことが大切です。
本記事では、失業保険をもらえる回数や受給要件、注意点について詳しく解説します。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
失業保険は何回ももらえる?

失業保険は、自己都合や会社都合の退職理由を問わず、受給回数に上限はありません。ただし、一定の条件を満たす必要があります。例えば、再就職してから一定期間が経過し、再び失業した場合でも条件を満たしていれば再受給が可能です。
失業保険の受給要件
失業保険の受給には回数の制限はありませんが、下記の条件を満たす必要があります。ポイントについて詳しく見ていきましょう。
雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
雇用保険は、失業中の生活を支えるための公的制度です。そのため、失業保険を受給するためには、まず雇用保険に加入し、保険料を支払っている必要があります。
具体的な条件は、以下のとおりです。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
離職前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間があること
失業保険を受け取るためには、離職前2年間に通算で12カ月以上の被保険者期間が必要です。この「被保険者期間」とは、以下の条件のどちらかを満たす月を1カ月としてカウントします。
- 賃金支払基礎日数が11日以上
- 労働時間が80時間以上
また、特定受給資格者(会社都合退職など)や特定理由離職者(契約期間満了など)の場合、条件は緩和され、離職前1年間に通算して6カ月以上の被保険者期間があれば受給資格を得られます。
就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること
失業保険は、再就職を目指す人への支援制度です。そのため、以下の条件を満たしている必要があります。
- 就労の意志があること
- 就労可能な状態であること
- ハローワークに求職の申し込みを行い、求職活動を行っていること
例えば、病気やケガで働けない場合は、受給資格を一時停止する手続きが必要です。医師の診断書を提出することで、受給期間を延長できる場合もあります。ハローワークでの失業認定日に、求職活動の実績を報告しなければなりません。少なくとも月に2回以上の求職活動実績が必要です。ここでの求職活動とは、求人への応募や面接、職業相談、各種セミナーへの参加が該当します。
失業保険を一度もらうと次はいつもらえる?
失業保険は、一度受給した後でも条件を満たせば再度受給が可能です。しかし、再受給には一定の期間と条件が設定されています。会社都合で退職した場合と自己都合で退職した場合で必要な期間が異なるため、それぞれのケースについて詳しく解説します。
会社都合退職の場合
会社の倒産や解雇など、会社側の理由で退職した場合は「特定受給資格者」として扱われます。会社都合退職は自己都合退職に比べて条件が緩和されているため、再就職先で6カ月以上の雇用保険加入期間があれば、再度失業保険の受給資格が得られます。
また、会社都合退職の場合、給付制限期間がなく待期期間満了後、すぐに受給が始まります。会社都合退職の場合は、再受給までのハードルが比較的低いと言えるでしょう。
自己都合退職の場合
一方、自己都合で退職した場合は「一般の受給資格者」として扱われます。この場合、再度失業保険を受給するためには、再就職先で12カ月以上の雇用保険加入期間が必要です。
再就職が早い場合、失業保険の代わりに再就職手当を受け取れる可能性もありますが、その場合も雇用保険の加入期間が必要です。自己都合退職は会社都合退職と比べて再受給の条件が厳しいため、退職前に十分な計画が求められます。
失業保険をもらう流れや手続き
失業保険を受給するためには、ハローワークでの手続きや必要書類の準備など、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、失業保険をもらうための具体的な流れと注意点について詳しく解説します。
必要書類を揃える
失業保険を申請する際には、まずハローワークで求職の申し込みを行う前に必要書類を揃えましょう。
以下は、退職した会社から渡される必要書類です。
- 雇用保険被保険者離職票-1・2
- 雇用保険被保険者証
下記書類は、個人で準備が必要です。
- 証明写真(たて3cm×よこ2.4cm、正面上半身)2枚
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 住所・氏名・年齢が確認できる本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1つ)
これらの書類は、不備があると手続きが遅れる原因となります。事前にチェックリストを作り、漏れがないように準備しましょう。
ハローワークで求職を申し込む
必要書類が揃ったら、ハローワークで求職の申し込みを行います。具体的な手順は以下のとおりです。
1.求職申込書に記入する
職種や希望条件などを記載します。
2.必要書類の提出、職業相談を行う
離職票や雇用保険被保険者証を提出し、相談員との面談を行います。
3.雇用保険説明会の日時が決定する
受給資格が決定すると、「失業等給付受給資格者のしおり」が渡されます。
求職申し込みの際には離職票の提出が必須です。失業保険の受給手続きを進めるためには、離職票が必須です。退職後、会社へすぐに離職票の発行を依頼しておきましょう。
また説明会の日程は申請日から7日後以降です。カレンダーにしっかりと記載しておくことが重要です。
待機期間を過ごす
ハローワークで受給資格が認定されると、7日間の待機期間が設けられます。この間は失業手当が支給されませんが、求職申し込みをした日からカウントが始まります。
この期間に働くと、就労と見なされ受給資格が失われる可能性が高い点に注意が必要です。短時間のアルバイトやパートを含めて一切の就労を控えましょう。
また、待機期間中に再就職が決まった場合は、再就職手当が支給されません。再就職手当は、待機期間終了後の再就職でしか受給できないため、手当の受給を考えている場合は、スケジュール調整が重要です。
雇用保険説明会に参加する
求職申し込みの際に案内される雇用保険受給説明会は、受給資格を維持するためにも参加が必須です。説明会では、失業保険の仕組みや受給条件、求職活動の進め方について詳しく説明されます。
持参するもの
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 印鑑
- 筆記用具
説明会での内容例
- 失業認定のスケジュール
- 求職活動の実績報告方法
- 不正受給のペナルティについて
説明会終了後には、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡されます。毎回の失業認定日に必要となるため、紛失しないよう注意しましょう。
失業認定日にハローワークを訪れる
失業認定日とは、ハローワークが失業の事実を認定し、失業手当を支給するための日です。通常、4週間に1度のペースで設定されます。 初回のみ、離職票を提出した日から約3週間後に設定され、認定されると最初の失業手当が振り込まれます。
失業認定日には、就職活動の実績を記載した申告書を提出します。少なくとも2回以上の求職活動実績が必要です。
やむを得ない理由で失業認定日を欠席する場合は、事前にハローワークへ連絡しましょう。再設定の依頼が可能です。
失業保険をもらうデメリット
失業保険は失業中の生活を支える大切な制度ですが、受給にはいくつかのデメリットもあります。事前に理解しておくべき3つのポイントを解説します。
雇用保険の加入期間がリセットされる
失業保険を受給すると、これまで積み上げてきた雇用保険の被保険者期間がリセットされます。その結果、再就職した後に再び失業した場合、再受給の条件を満たせなくなる可能性を考えておきましょう。
短期間の退職は、失業保険を受け取れないリスクが高まります。特に、契約社員や派遣社員など、雇用期間が限られている場合は注意が必要です。
受給までに時間がかかる
特に自己都合退職の場合、7日間の待機期間と1カ月の給付制限期間があり、失業保険受給までに一定の期間が発生します。
その間、収入は一切入らないため、生活費や家賃などを自己資金で賄わなければなりません。また、貯蓄がない場合や急な支出がある場合には、経済的に厳しい状況に追い込まれるリスクもあります。
転職活動のモチベーションが下がる
失業保険の受給により一定の収入が確保される点はメリットではあるものの、金銭的な余裕により、安心してしまいがちです。「まだ受給期間があるから」と、求人探しや面接の意欲が低下した結果、失業期間が長引き、職務経歴に空白期間ができる可能性もあります。
失業保険をもらうメリット
一方、失業保険をもらうことには多くのメリットもあります。具体的な3つのメリットを紹介します。
経済的な負担が少なくなる
失業保険は、失業中の生活を支えるための重要な資金源です。生活費や家賃、公共料金の支払いに大きな助けとなります。
特に養う家族がいる場合や住宅ローンを抱えている場合、経済的な負担を大幅に軽減できます。
一定の収入が確保されるため、心にも余裕が生まれやすく、予期せぬ出費にも対応が可能です。特に、長期間の転職活動を予定している場合には、この収入が精神的な安定にもつながります。
落ち着いて転職活動できる
失業保険があることで、急いで就職先を決める必要がなくなります。金銭的な理由による「とりあえず就職」「手当たり次第応募」と焦る必要がないため、適性の低い職場や待遇の悪い会社に就職するリスクを回避できるでしょう。
例えば、求人情報をじっくり調べ、企業の評判や職場環境を確認する余裕も生まれます。また職業訓練の受講やスキルアップの時間確保により、次の職場で活かせるスキルを習得することも可能です。失業保険は、長期的なキャリアを考えた計画的な転職活動を支えてくれる存在と言えるでしょう。
「再就職手当」を受け取ることができる
失業保険受給中、早期に再就職が決まった場合再就職手当を受け取れる可能性があります。再就職手当は、失業保険の給付日数が一定以上残っている場合に支給される手当です。
早期の再就職を促進するため、手当の支給率が高めに設定されています。また給付額は、残りの給付日数に応じて計算されるため、まとまった金額が受け取れる点もポイントです。
再就職手当は、転職後の収入が安定するまでの間に利用できます。初任給が入るまでの生活費を補填できるため、活用しましょう。
失業保険を受け取るときの注意点

失業保険は、再就職までの生活を支える重要な制度ですが、受給にはいくつかの注意点があります。自己都合退職の場合の給付制限や、時効、アルバイトに関する制限などを理解し、トラブルから身を守りましょう。
自己都合退職の場合は給付制限期間がある
自己都合で退職した場合、給付制限期間がある点に注意が必要です。ハローワークで求職の申し込みを行い、受給資格が決定した日から7日間の待機期間が設けられます。この期間中は、失業保険は支給されません。
自己都合退職の場合、待機期間後に給付制限があります。ただし、2025年4月1日以降の給付制限期間は、これまでの2カ月間から1カ月間に短縮されます。そのため、実際に失業保険が支給開始となるタイミングの目安は、退職後約1カ月と1週間後です。
失業保険には1年間の時効がある
失業保険の受給権には、離職日の翌日から1年間という時効があります。この期間内に手続きを行わないと、受給権が消滅してしまいます。
離職後に病気やケガで長期間働けない場合でも、時効は進行します。時効を延長できるケースもありますが、延長手続きは離職後すぐに行う必要があります。
さらに、受給期間の延長を希望する場合は、退職後、30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降に手続きを進める必要があります。延長できるのは最大3年間までとなっているため、注意しましょう。
受給期間中のアルバイト・パートには制限がある
失業保険の受給期間中にアルバイトやパートを行うことは可能ですが、いくつかの制限があります。制限を知らずにアルバイトをすると、手当が減額されたり支給停止となったりするリスクがあります。
1日の労働時間が4時間以上の場合、その日は「就労」と見なされ、失業保険の支給が先送りされます。 逆に、4時間未満の場合は「就労」とは見なされませんが、別の条件が適用されます。
アルバイト収入と失業保険の基本手当の合計から控除額(1,354円)を差し引いた金額が、前職の1日分の賃金の80%を超えると、手当が減額になります。(※)。また収入には報告義務があり、未報告の場合は不正受給として返還やペナルティの対象になる点に注意しましょう。
※1,354円は令和6年8月1日時点の控除額で、毎年変更されます。
失業保険でよくある質問
失業保険については、受給条件や手続きが複雑なため、多くの疑問が寄せられます。特に問い合わせが多い質問について詳しく解説します。
失業保険をもらったあとに働かなくてもいいですか?
失業保険は、再就職を支援するための制度です。そのため、受給中は積極的に求職活動を行い、就職の意思があることを証明しなければなりません。
4週間ごとの失業認定日には、求職活動の実績報告が必要です。求職活動実績がない場合、受給資格を失う可能性が高くなります。
受給後長期間働かないと、年金受給額や社会保険の加入期間にも影響を及ぼします。特に、国民年金の保険料未納が続くと、将来の年金受給額が減少するリスクがあります。このため、失業保険を受け取った後も、計画的に転職活動を進めることが重要です。
失業保険をもらうと年金はどうなりますか?
失業保険の受給そのものは、年金の受給資格や受給額に直接的な影響を与えません。しかし、失業中は厚生年金の被保険者資格を失います。
国民年金の第1号被保険者への切り替えを行い、保険料を支払う必要があります。ただし、収入が減少して保険料の支払いが難しい場合は、保険料免除制度の利用が可能です。免除された期間も年金の受給資格期間に含まれますが、受給額は減額されます。
再就職が決まった場合の失業保険はどうすればいいですか?
再就職が決まったら、速やかにハローワークに報告しましょう。
次回の認定日よりも就職日が後の場合は、指定の失業認定日にハローワークを訪れ、就職の報告を行います。 就職日が認定日より前の場合は原則として就職日の前日にハローワークで手続きを行います。 就職先に「採用証明書」の記入を依頼し、提出しましょう。
所定給付日数が3分の1以上残っている場合、早期再就職で再就職手当を受け取れる可能性があります。報告手続きを怠ると、再就職手当を受け取れないだけでなく、失業保険の不正受給と見なされるリスクもあるため注意が必要です。
失業保険を一度もらうと育休手当はどうなりますか?
失業保険と育児休業給付金(育休手当)は同時に受給できません。育休手当は、雇用保険の被保険者であることが条件ですが、失業保険を受給している間は被保険者資格が喪失しています。
失業保険受給中に妊娠・出産した場合は、再就職後に育児休業を取得するために必要な条件を満たす必要があります。逆に、育休手当を受給中は失業保険の申請ができません。
障害がある場合でも失業保険を受け取れますか?
障害がある方でも、雇用保険の被保険者かつ受給資格を満たしていれば、失業保険を受け取ることが可能です。
「就職困難者」と認定されると、通常90日の所定給付日数が最大360日まで延長されるなどの特例があります。 職業訓練や就職支援の専門相談員によるサポートも受けられる点が特徴です。
まとめ
失業保険は、再就職までの生活を支える大切な制度です。受給の条件や手続きにはいくつかの注意点がありますが、適切に活用することで経済的な不安を軽減しながら落ち着いて転職活動を行うことができます。また、早期に再就職が決まった場合には再就職手当を受け取れる点もメリットです。
失業保険をはじめとする社会保険の手続きは煩雑なため、効率よく進めるためには専門的なサポートが役立ちます。失業保険の受給手続きに不安がある方は、「社会保険給付金サポート」のご利用をご検討ください。専門家のアドバイスを受けることで、申請の不備や受給漏れを防ぎ、スムーズに給付金を受け取ることが可能です。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
おすすめの関連記事
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 新型コロナウイルスについて
- 社会保険について
- 退職代行について
- 税金について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
障害年金を知ろう
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは必須?スムーズな業務引き継ぎのポイント
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
テーマ
- クレジットカード
- 資格取得
- 退職願
- 職業訓練受講手当
- 自己PR
- 社会保険給付金
- 退職代行
- アルバイト
- 精神疾患
- 退職届
- インフルエンザ
- 確定申告
- 職業訓練受講給付金
- 退職代行サービス
- 雇用保険
- うつ病
- 面接
- 感染症
- 保険料
- 退職給付金
- ブラック企業
- 健康保険
- 統合失調症
- 障害手当金
- 引っ越し
- 社会保障
- ハローワーク
- ハラスメント
- 年金
- 契約社員
- 自己都合
- 社宅
- 就職
- 就業手当
- パワハラ
- 転職活動
- 弁護士
- 会社都合
- 障害者手帳
- 労働基準法
- 傷病手当
- モラハラ
- 転職サイト
- 公的貸付制度
- 失業給付
- 精神保険福祉手帳
- 雇用契約
- 退職コンシェルジュ
- セクハラ
- 職務経歴書
- 生活福祉資金貸付制度
- 新型コロナウイルス
- 労災
- 内定
- 社会保険給付金サポート
- 障害年金
- 人間関係
- 通勤定期券
- 有給消化
- 産休
- 就労移行支援
- 雇用保険サポート
- 引き継ぎ
- スタートアップ
- 不支給
- 休職
- 育児休暇
- 業務委託
- 退職手当
- 給与
- 転職
- 等級
- 免除申請
- 解雇
- 社会保険
- 残業代
- 違法派遣
- 離職票
- 適応障害
- 大企業
- 福利厚生
- 退職金
- 派遣契約
- 労務不能
- 住宅確保給付
- 中小企業
- 失業手当
- 会社都合退職
- 障害厚生年金
- 傷病手当金
- 給付金
- ベンチャー企業
- 就職困難者
- 自己都合退職
- 失業保険
- 年末調整
- 職業訓練
- 会社倒産
- 再就職手当
- 退職
- ブランク期間
- 障害者控除
- 再就職
- 退職勧奨
- 転職エージェント
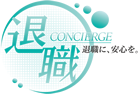




 サービス詳細
サービス詳細