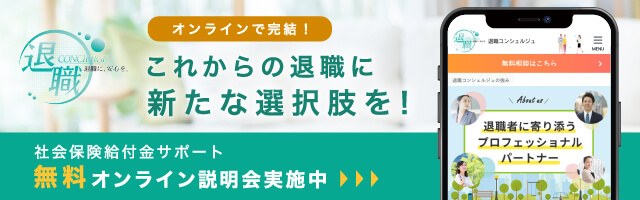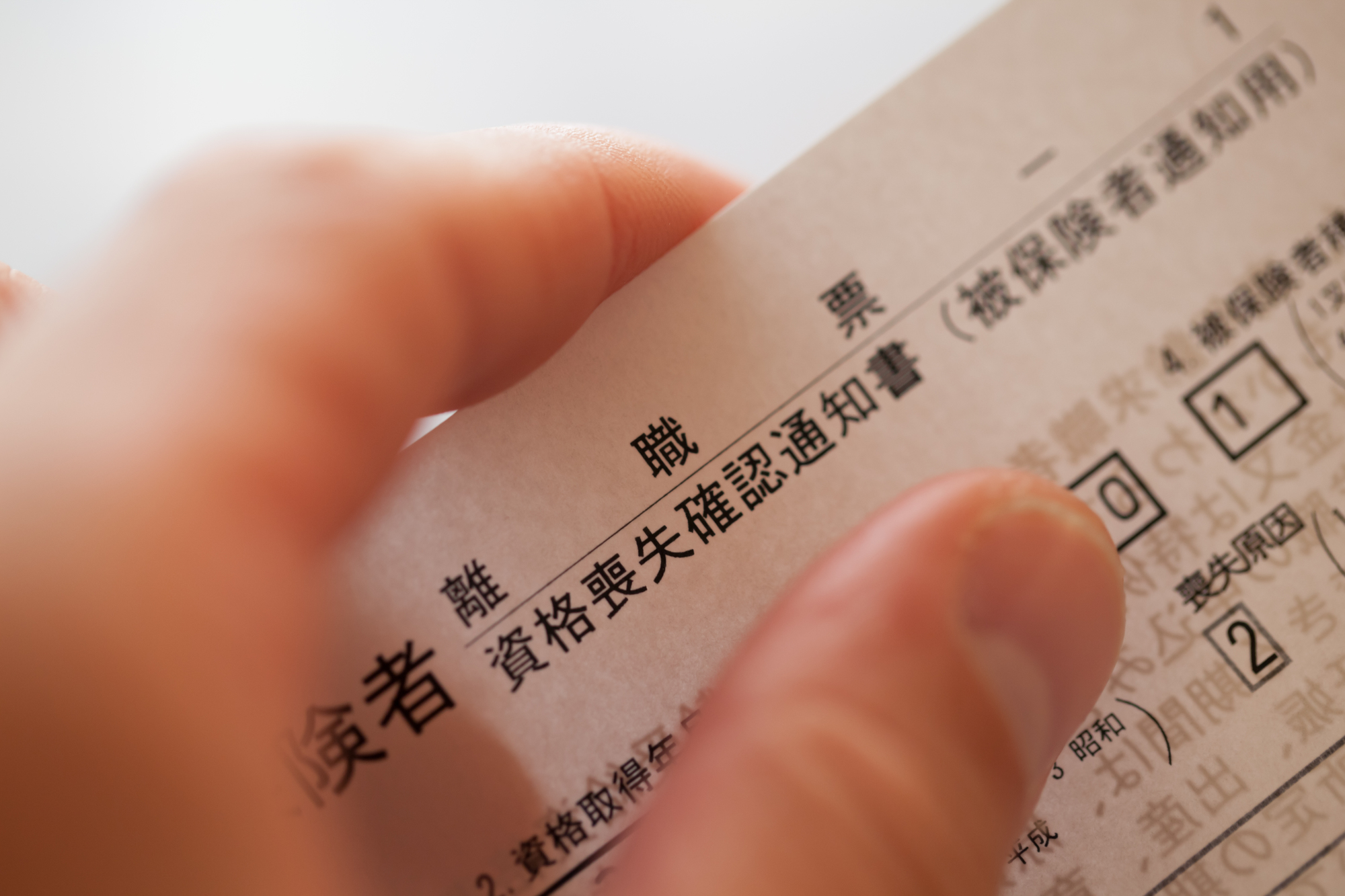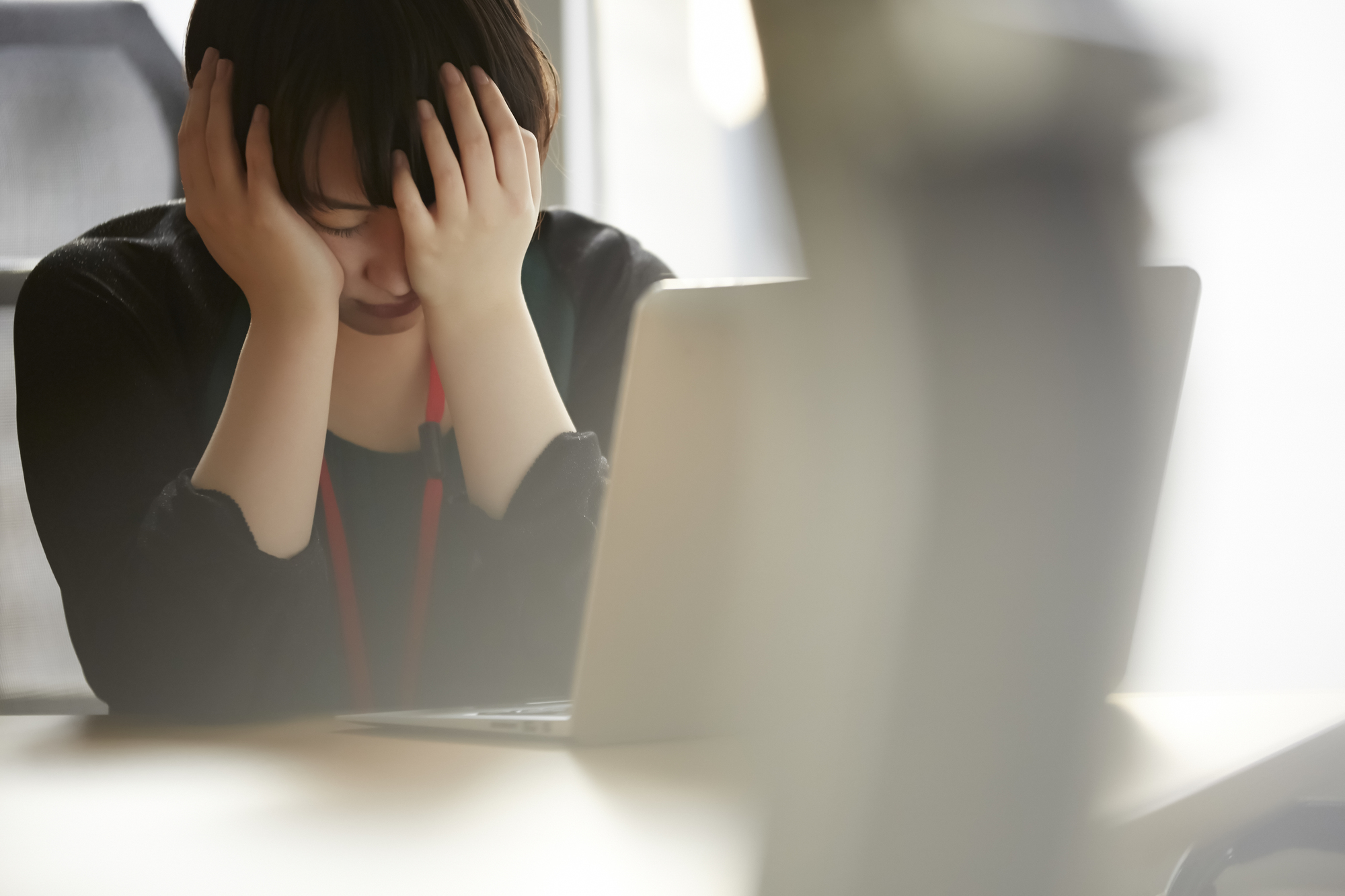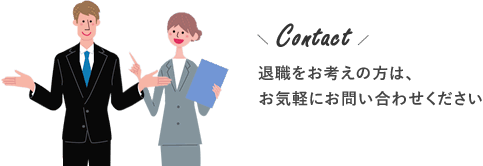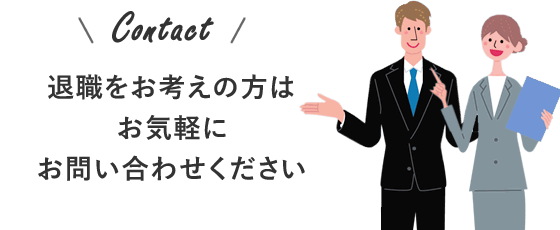2025.04.03
給付金について
失業保険をもらえないケースとは?もらえる条件も解説

失業保険は失業後の生活を支える重要な収入源となる制度ですが、もらえないケースもあります。では、失業保険の受給を見越して退職したものの受け取れない場合に、代わりとなる制度はあるのでしょうか。
本記事では、失業保険をもらえない7つの代表的なケースと、失業保険をもらうための条件、もらえる日数や金額を解説します。また受給手続きの流れや、もらわないほうがいい人の例、もらえない場合に検討できる制度も紹介しますので、失業保険をもらえるかどうか不安な方は、参考にしてください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
失業保険がもらえないケース

失業保険をもらうには、後述するように雇用保険への加入期間や就労の意思などが求められます。
以下のケースに該当する場合は、失業保険がもらえないため注意しましょう。
就労の意思と能力がない
失業保険の受給には、就労の意思と能力が求められ、すぐに働ける状態であることが条件です。そのため、退職後に求職活動を行わない場合や、病気、怪我、妊娠・出産、育児などですぐに働ける状態にない場合などで受給資格を満たさないと判断されるケースでは、失業保険を受け取れません。
ただし、これらの理由で離職した場合であっても正当な理由であると認められるなど一定の要件を満たせば、特定理由離職者として認定され、失業保険を受け取れる可能性があります。
雇用保険の被保険者期間が足りていない
失業保険を受給するには、離職前の2年間に通算して12ヵ月以上の雇用保険の被保険者期間が必要です。そのため、新卒で入社したものの12ヵ月未満で自己都合退職した場合などは、この条件を満たさないので受給資格を得られません。
ただし、勤務先の倒産や解雇などのやむを得ない事情で離職した場合は、離職前の1年間に通算して6ヵ月以上の被保険者期間があれば失業保険を受給可能です。
ハローワークで失業認定を受けていない
失業保険の受給には、4週間に一度、ハローワークで失業認定を受けなければなりません。
失業認定を受けるには、ハローワークから指定された認定日に「失業認定申告書」を提出し、前回以降の期間における求職活動の状況を報告する必要があります。この手続きを怠ると、失業状態であると認められないため、失業保険を受給できなくなります。
副業を行っている
副業を行っている場合も失業保険をもらえません。失業期間中に副業を行っている場合、その労働時間や収入が一定以上になると失業状態とみなされず、受給が制限されることがあるためです。
特に、週20時間以上の労働や31日以上の雇用見込みがある場合は、雇用保険の加入条件を満たす状態であり、失業保険の受給資格を失う可能性があります。
なお、副業などで収入があるにもかかわらず、虚偽の申請をした場合は不正受給にあたります。すでに受給した金額の返還やペナルティが課せられるので正しく申告しましょう。
すでに年金を受給している
特別支給の老齢厚生年金や退職共済年金などを65歳未満で受給している場合は、雇用保険の失業給付と同時に受け取ることはできません。
ハローワークで求職の申し込みを行うと、年金支給が全額停止されるので注意が必要です。どちらを受給するかは、受給額や個々の状況を考慮して判断する必要があるため、年金の受給は慎重に検討しましょう。
傷病手当金を受給している
傷病手当金を受給している場合も、原則的には失業保険をもらえません。
傷病手当金は病気や怪我で働けない場合に支給されるもので、受給中は就労可能な状態ではないと判断されます。この場合、失業保険の受給条件である「就労の意思と能力」を満たさず、同時に受給することはできないためです。
傷病手当金を受給しているケースでは、健康状態が回復して就労可能となった後に失業保険の受給手続きを行うのが一般的です。
自営業を開始した
会社を退職後に、自営業を開始した場合はすでに就業しているとみなされるため失業保険の受給資格を失います。
ただし、失業期間が開業準備中に該当し、かつ求職活動を行っている場合は、失業状態と認められることもあります。
自営業を開始した状態であるかどうかは具体的な状況によって判断が異なるため、ハローワークに相談することが望ましいでしょう。
失業保険がもらえる条件
失業保険を受給するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
- 離職前2年間に12ヵ月以上の雇用保険の被保険者期間があること
- 就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること
雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
そもそも雇用保険は、労働者が失業した際に生活の安定を図るための公的な保険制度です。そのため、失業保険の受給に際して雇用保険に加入していることが前提になります。
なお、雇用保険に加入するには、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ同一の事業主からの31日以上の雇用見込みがあることが必要です。
離職前2年間に12ヵ月以上の雇用保険の被保険者期間があること
失業保険を受給するには、離職前の2年間に通算して12ヵ月以上の被保険者期間が必要です。
被保険者期間は、在職時の各月における賃金支払基礎日数が11日以上、または労働時間が80時間以上ある月を1ヵ月として計算します。
ただし、特定受給資格者(倒産などの会社都合退職の場合)や特定理由離職者(派遣社員の契約期間満了など)の場合は、離職前の1年間に通算して6ヵ月以上の被保険者期間があれば受給資格を得られます。そのため、この期間を満たしているケースでは失業保険の受給が可能です。
就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること
失業保険は再就職を目指す人を支援する制度であり、ハローワークによって受給者には就労の意志と能力があり、求職活動を行っていると認められた場合に受給が可能です。
この条件を満たすには、ハローワークに対して求職の申し込みを行い、積極的に求職活動を行っている必要があります。例えば、求人への応募や面接、職業相談や各種セミナーへの参加などが求職活動に該当します。
失業保険をもらえる日数やタイミング
失業保険をもらえる日数や支給のタイミングは、前職の退職理由によって変わります。ここでは、自己都合退職と会社都合退職に分けて解説します。
自己都合退職の場合
会社を辞めた理由が自己都合の場合における所定の給付日数は90日から150日です。
所定給付日数は、以下の表に示すとおり、雇用保険に加入していた期間によって異なります。
|
離職時の年齢 |
被保険者期間 |
||
|
1年以上※ 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
|
|
65歳未満の場合 |
90日 |
120日 |
150日 |
なお、特定理由離職者の場合は、被保険者期間が1年未満であっても、90日となります。
自己都合退職において失業手当を受給できるタイミングは、7日間の待期期間経過後、さらに2ヵ月の給付制限期間の経過後です。なお、2025年4月以降は給付制限は1ヵ月に短縮されます。
会社都合退職の場合
会社を辞めた理由が会社都合の場合における、所定の給付日数は90日から330日です。
会社都合とは、倒産や人員削減(リストラ)による解雇、給与未払いなど、受給者にとってやむを得ない理由を指します。
次の表のとおり、会社都合退職の場合は、雇用保険に加入していた期間と受給者の年齢によって給付日数が変わります。
|
離職時の年齢 |
被保険者期間 |
||||
|
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
|
|
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
– |
|
30歳以上 35歳未満 |
90日 |
120日 |
180日 |
210日 |
240日 |
|
35歳以上 45歳未満 |
90日 |
150日 |
180日 |
240日 |
270日 |
|
45歳以上 60歳未満 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
|
60歳以上 65歳未満 |
90日 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
失業保険の受給金額
失業保険の受給金額は、「基本手当日額 × 給付日数」によって決定されます。詳しくは後述しますが、離職前の賃金の5〜8割程度が一般的な受給額です。
賃金日額を計算する
はじめに受給金額のベースとなる賃金日額を計算します。
賃金日額とは、離職前の直近6ヵ月間において支払われた賃金の総額を180で割った金額のことです。ここでの賃金とは、基本給、残業代、通勤手当や住宅手当などの各種手当が含まれ、賞与や祝い金、退職金といった臨時的な賃金は含まれないため、計算する際は気をつけましょう。
基本手当日額を計算する
続いて、基本手当日額を計算します。基本手当日額は、先ほど算出した賃金日額に、50%〜80%の給付率をかけ合わせて「基本手当日額」を求めます。
なお、給付率は賃金日額が低いほど高く設定されます。具体的な給付率は厚生労働省の基準に基づいて決定され、ハローワーク窓口でも確認可能です。
基本手当総額を計算する
基本手当日額を算出したら、所定給付日数をかけ合わせて基本手当総受給額を計算します。
所定給付日数は、失業保険をもらえる日数で説明したとおり、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢などの条件によって異なります。
例えば、自己都合退職の場合、被保険者期間が1年以上5年未満であれば90日が所定給付日数です。
仮に、離職前6ヵ月間の賃金総額が180万円で給付率が60%、所定給付日数が120日の場合を想定して、具体的に計算してみましょう。
賃金日額:180万円÷180日=1万円
基本手当日額:1万円×60%=6,000円
基本手当総受給額:6,000円×120日=72万円
なお、基本手当日額は以下の表に示すとおり、上限額が設定されています。
(令和6年8月1日時点)
|
30歳未満 |
7,065円 |
|
30歳以上45歳未満 |
7,845円 |
|
45歳以上60歳未満 |
8,635円 |
|
60歳以上65歳未満 |
7,420円 |
失業保険をもらう流れ
失業保険は、次の流れで申請します。
- 必要書類を揃える
- ハローワークで求職を申し込む
- 待機期間を過ごす
- 雇用保険説明会に参加する
- 失業認定日にハローワークを訪れる
必要書類を揃える
失業保険の申請にあたっては、ハローワークで求職申し込みを行う必要があります。事前に以下の必要書類を準備しましょう。
- 雇用保険被保険者離職票-1・2
- 雇用保険被保険者証
- 証明写真(たて3cm×よこ2.4cm、正面上半身)×2
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 住所・氏名・年齢が確認できる本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1つ)
ハローワークで求職を申し込む
書類がそろえばハローワークで求職の申し込みを行います。ハローワーク窓口での具体的な流れは以下のとおりです。
- 求職申込書に記入する
- 必要書類の提出、職業相談を行う
- 雇用保険説明会の日時が決定する
失業保険を受ける場合は求職の意思があることが要件です。ハローワークの窓口で離職票の提出と求職の申し込みを行いましょう。
受給資格が決定すると「失業等給付受給資格者のしおり」が交付されます。さらに、後日開催される雇用保険説明会についても案内を受けます。
雇用保険説明会には必ず出席しなければなりません。申請日から7日後以降に開催されるので、忘れずに日時をメモしておきましょう。
待機期間を過ごす
ハローワークで受給資格が認められると、申し込み日から7日間の待機期間が設けられます。この7日間は、失業状況を調査する期間であり、一切の就労が禁止されます。例えば、短時間の勤務やアルバイトも就労とみなされるため、注意が必要です。
退職後すぐに転職先が見つかった場合など、求職申し込みをした日からの失業期間が7日に満たない場合は、失業保険は給付されません。
また、失業手当の給付日数が残っているタイミングで再就職する場合は、残りの日数に応じて再就職手当を受け取れます。ただし、7日間の待期期間中に入社日を迎えてしまうと、再就職手当を受け取る事はできなくなるため、再就職手当の受給を検討している場合はご注意ください。
雇用保険説明会に参加する
失業保険の受給には、求職の申し込み時に案内された雇用保険説明会に参加する必要があります。雇用保険説明会では失業保険の概要や受給までの流れ、求職活動の方法などが詳しく説明されるので、この機会に理解を深めましょう。
なお、雇用保険説明会の参加時は、以下の持ち物を忘れずに持参してください。
- 雇用保険受給資格者のしおり(求職申込時に交付)
- 印鑑
- 筆記用具
説明会が終わると「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付され、次にハローワークを訪問する初回の失業認定日が案内されます。
失業認定日にハローワークを訪れる
「失業認定日」とは、ハローワークが失業認定申告書や期間中の活動実績などによって失業の事実を認定する日のことです。
当日は、失業認定申告書を提出し、求人探しや応募、面接、再就職セミナーへの参加など、就職活動の実績を報告しなければなりません。
通常は、失業認定日は4週間ごとに1日設定され、ハローワークから指定されます。また、通常、初回の失業認定日は、離職票をハローワークに提出した日から約3週間後に設定されます。
失業保険をもらわないほうがいい人
失業保険は受け取ることで、失業期間中に生活を送るための収入源となりますが、場合によっては受給しないほうがいい場合もあります。
ここでは、失業保険をもらわないほうがいい人の代表例を紹介します。
雇用保険の被保険者期間を維持したい人
失業保険を受給すると、これまでの雇用保険の被保険者期間がリセットされてしまいます。そのため、再就職後に短期間で再度離職すると受給資格を満たさなくなる可能性があるため注意が必要です。
被保険者期間を継続させて将来の受給資格を確保したい場合は、受給を見送る選択を検討しても良いでしょう。
早期の再就職を目指す人
失業保険の受給中は、求職活動の報告や失業認定などのハローワークでの手続きが必要であり、これらが就職活動の負担となる可能性が考えられます。
また、受給によって一時的な収入が得られると就職活動のモチベーションが低下し、再就職が遅れる可能性もあるため、早期の再就職を目指す人は、失業保険をもらわないほうがいいでしょう。
受給手続きの手間を避けたい人
失業保険の受給には、ハローワークでの手続きや原則として4週間に1度、定期的な求職活動の報告を行わなければなりません。
このように、受給手続きには時間と労力を要するため、迅速に再就職先を見つけたい場合や、手続きの負担を避けたい場合には、受給を見送ることも選択すべきでしょう。
失業保険の受給手続きに関する手間を省きたい方は「社会保険給付金サポート」のご利用をぜひご検討ください。専門家に支援してもらえるので、効率的に手続きを進められるでしょう。
失業保険がもらえない場合に検討できる制度

雇用保険の加入期間を満たさないなど、失業保険がもらえない場合であっても、収入維持のために検討できる制度はあります。
ここでは、以下の制度について解説します。
- 傷病手当金
- 求職者支援制度
- 生活困窮者自立支援制度
- 障害年金
- 生活福祉資金貸付制度
- 生活保護
傷病手当金
傷病手当金とは、健康保険に加入している被保険者が業務外の病気やけがで働けなくなった場合に受給できる手当金のことです。受給条件や金額、期間などは以下のとおりです。
傷病手当金の受給条件
傷病手当金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 業務外の病気やケガで療養中であること。
業務上や通勤途中の病気やケガは労働災害保険の対象になります。また、美容整形手術など健康保険の対象外の治療も除きます。
2. 療養のため労務不能であること。
労務不能とは、今まで従事していた業務ができない状態のことで、医師の意見や業務内容を考慮して判断されます。
3. 4日以上仕事を休んでいること。
療養開始から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目からが支給対象になります。
4. 給与の支払いがないこと。
傷病によって仕事を休んでいる期間に対して給与が一部支給されている場合は、その分が減額されて傷病手当金が支給されます。
傷病手当金の受給金額
傷病手当金の1日当たりの金額は次の計算式で求められます。
|
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2 |
実際に想定される傷病手当金の金額を月給をベースに標準報酬月額を割り出し、一覧にまとめたものが以下の表です。
|
月給 |
標準報酬月額 |
傷病手当金(日額) |
傷病手当金(月額) |
|
50,000 |
58,000 |
1,289 |
38,670 |
|
100,000 |
98,000 |
2,178 |
65,340 |
|
150,000 |
150,000 |
3,333 |
99,990 |
|
200,000 |
200,000 |
4,444 |
133,320 |
|
250,000 |
260,000 |
5,778 |
173,340 |
|
300,000 |
300,000 |
6,667 |
200,010 |
|
350,000 |
360,000 |
8,000 |
240,000 |
|
400,000 |
410,000 |
9,111 |
273,330 |
傷病手当金の受給期間
健康保険の傷病手当金が支給されるタイミングは、病気やケガで休んだ期間のうち、最初の3日間を除いた4日目からです。また、受給期間は、手当の支給日数が合計して1年6か月になるまでとなります。
退職後に健康保険の資格を喪失しても、過去の保険の加入期間が継続して1年以上ある場合には傷病手当金を受給できる可能性があります。ただし、会社の加入している健康保険組合によってルールが異なるため、専門家に確認を行いましょう。
傷病手当金の申請方法
健康保険の傷病手当金は、次の手順で申請します。
- 「健康保険傷病手当金支給申請書」を用意し記入する
- 勤務先と医療機関に必要な項目を記載してもらう
- 必要書類を揃え健康保険組合もしくは協会けんぽに提出する
失業手当と傷病手当金は併給できる?
失業保険の手当と傷病手当金の併給はできません。失業保険の給付金は労働の意思・能力があることが要件であり、傷病手当金の労務不能の条件と相反するためです。
求職者支援制度
求職者支援制度も失業保険をもらえない時に活用できる制度です。
求職者支援制度とは、失業保険の受給資格がない求職者や失業保険の受給期間が終了した人を対象に、職業訓練と生活費支援を提供する制度です。
求職者支援制度を利用するには、以下の4つの条件を満たす必要があります。
- ハローワークに求職の申し込みをしている
- 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でない
- 労働の意思・能力がある
- ハローワークによって職業訓練などの支援が必要であると認められている
職業訓練を通じて再就職に必要なスキルを身につけられるよう支援するもので、職業訓練の受講中に「職業訓練受講手当」「通所手当」「寄宿手当」の3つが支給されます。
- 職業訓練受講手当 月額10万円
- 通諸手当 職業訓練校までの交通費(最大月額42,250円)
- 寄宿手当 職業訓練を受けるために同居の配偶者などと別居して寄宿する費用(10,700円)
生活困窮者自立支援制度
失業保険をもらえない場合は、生活困窮者自立支援制度を利用する方法もあります。
具体的な事業内容は、以下のとおりです。
|
事業名 |
内容 |
|
自立相談支援事業 |
地域の支援員に相談することで、自立に向けた具体的なプランを作成して、その内容に応じた支援を実施 |
|
住居確保給付金の支給 |
求職活動を行うことを条件に、家賃相当額を一定期間支給 |
|
就労準備支援事業 |
ただちに就労が難しい人を対象に、6ヵ月から1年のプログラムを実施し、一般就労に向けた基礎能力を養い、就労機会を提供 |
|
家計改善支援事業 |
早期の生活再生を目指して家計を可視化する計画書を作成し、家計を立て直すための相談支援や関係機関との連携、貸付のあっせんなどを実施 |
|
就労訓練事業 |
ただちに就労が難しい人を対象に状況に応じた作業機会の提供や個別の就労支援プログラム、就労訓練を提供 |
|
生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業 |
生活困窮世帯に属する子どもの学習支援や生活習慣の形成、居場所づくり、進学支援などを子どもと保護者に提供 |
|
一時生活支援事業 |
住居のない人や不安定な人を対象に、宿泊場所や移植を一定期間提供し、退所後に向けた就労支援を実施 |
障害年金
障害年金は、国民年金や厚生年金の被保険者が一定の障害状態になったときに支給される公的年金です。
ストレスによる体調不良が長期化して日常生活や労働に支障をきたす場合は、障害年金の対象となる可能性があります。
障害年金の受給には、初診日において年金保険料の納付要件を満たしていること、障害認定日において所定の障害等級に該当することなどが条件となります。
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は、生活再建のための資金を低金利または無利子で貸し付ける制度です。
収入の減少や失業により生活資金が不足する場合は、各都道府県の社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付制度を利用できます。
生活保護
生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を保証して、自立を助長することを目的に、日々の生活に困窮している人を対象に、その程度に応じて必要な保護を行う制度です。
生活保護の受給要件は、世帯における衣服代や食費、家賃などの最低生活費が国が定める保護基準に満たないことです。最低生活費は、世帯人数や年齢、居住地域の等級に応じて計算されます。
受給金額は、最低生活費より、世帯全員の収入や年金などの手当て、給付金を差し引いた金額が保護費として振り込まれます。
具体的な扶助の内容は、以下の8種類です。
- 生活扶助(生活費) 世帯人数に相応の食費・光熱費
- 住宅扶助(家賃) 家賃や地代、修繕費などの住宅に要する費用
- 教育扶助(教育費) 小学校・中学校に就学するための学用品費・給食費
- 医療扶助(医療費) 保険適用内の診察・手術費用、薬代のうちの自己負担分
- 介護扶助(介護費用) 居宅介護費・福祉用具費・施設介護費など、介護にかかる費用のうちの自己負担分
- 出産扶助(出産費用) 指定医療機関や助産所での出産費用
- 生業扶助(就労に必要な費用)高校就学に際する教材費・通学
- 交通費・入学準備金や就労に際する技能習得費・就職支度費など
- 葬祭扶助(葬祭費) 火葬式を行う際の最低限の費用・葬祭にかかる費用
まとめ
失業保険を受給するには、就労の意思と能力があるとハローワークから認められるほか、離職前の2年間に通算して12ヵ月以上の雇用保険の被保険者期間、および加入期間中に保険料を支払っていることが条件になります。
そのため、就労の意思や能力がないケースや被保険者期間が足りていないケース、ハローワークでの失業認定を受けていないケースでは失業保険をもらえないため注意が必要です。
失業保険の受給にはハローワークでの求職申し込みや、4週間に1度の失業認定などが必要なため、手続きが煩雑に感じる方もいるでしょう。「社会保険給付金サポート」では、経験豊富な専門家による手続きのサポートを実施し、スムーズに受給できるよう支援しております。無料オンライン説明会も実施しておりますので、ぜひご利用をご検討ください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
おすすめの関連記事
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 新型コロナウイルスについて
- 社会保険について
- 退職代行について
- 税金について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
障害年金を知ろう
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは必須?スムーズな業務引き継ぎのポイント
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
テーマ
- クレジットカード
- 資格取得
- 退職願
- 職業訓練受講手当
- 自己PR
- 社会保険給付金
- 退職代行
- アルバイト
- 精神疾患
- 退職届
- インフルエンザ
- 確定申告
- 職業訓練受講給付金
- 退職代行サービス
- 雇用保険
- うつ病
- 面接
- 感染症
- 保険料
- 退職給付金
- ブラック企業
- 健康保険
- 統合失調症
- 障害手当金
- 引っ越し
- 社会保障
- ハローワーク
- ハラスメント
- 年金
- 契約社員
- 自己都合
- 社宅
- 就職
- 就業手当
- パワハラ
- 転職活動
- 弁護士
- 会社都合
- 障害者手帳
- 労働基準法
- 傷病手当
- モラハラ
- 転職サイト
- 公的貸付制度
- 失業給付
- 精神保険福祉手帳
- 雇用契約
- 退職コンシェルジュ
- セクハラ
- 職務経歴書
- 生活福祉資金貸付制度
- 新型コロナウイルス
- 労災
- 内定
- 社会保険給付金サポート
- 障害年金
- 人間関係
- 通勤定期券
- 有給消化
- 産休
- 就労移行支援
- 雇用保険サポート
- 引き継ぎ
- スタートアップ
- 不支給
- 休職
- 育児休暇
- 業務委託
- 退職手当
- 給与
- 転職
- 等級
- 免除申請
- 解雇
- 社会保険
- 残業代
- 違法派遣
- 離職票
- 適応障害
- 大企業
- 福利厚生
- 退職金
- 派遣契約
- 労務不能
- 住宅確保給付
- 中小企業
- 失業手当
- 会社都合退職
- 障害厚生年金
- 傷病手当金
- 給付金
- ベンチャー企業
- 就職困難者
- 自己都合退職
- 失業保険
- 年末調整
- 職業訓練
- 会社倒産
- 再就職手当
- 退職
- ブランク期間
- 障害者控除
- 再就職
- 退職勧奨
- 転職エージェント
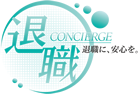




 サービス詳細
サービス詳細