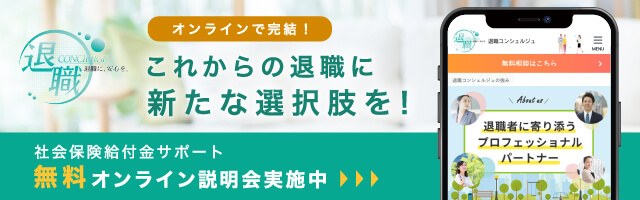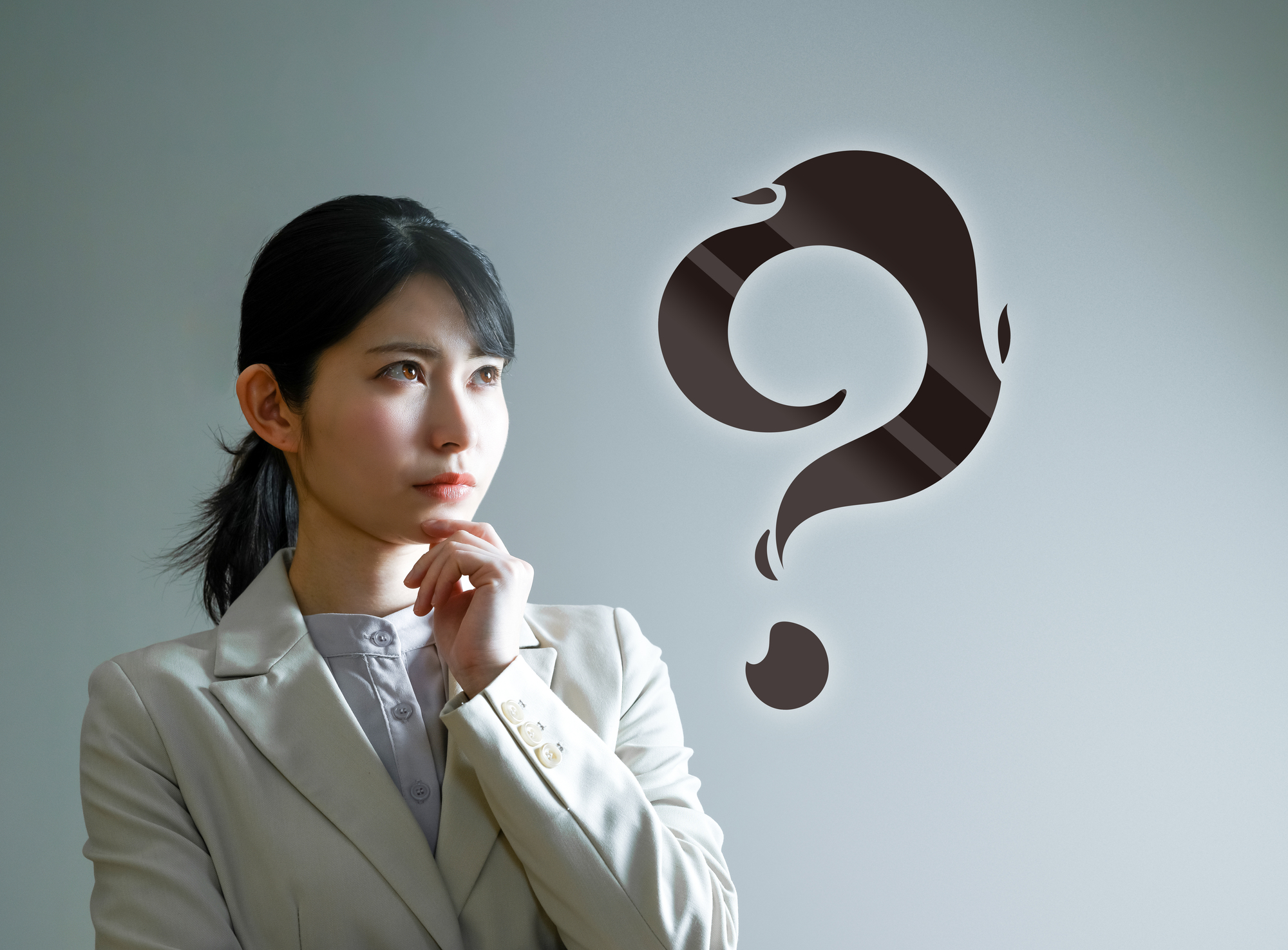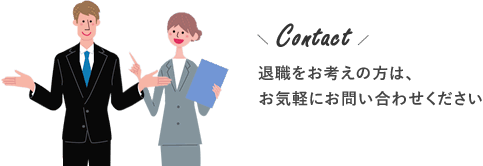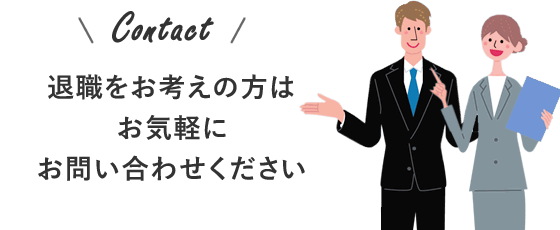2025.04.02
社会保険について
傷病手当と失業保険どちらが得?それぞれを比較して紹介

雇用保険の給付金には、失業保険のほかに傷病手当があります。傷病手当は、ハローワークで求職の申し込みをした後に病気やけがで働けなくなった場合に支給されますが、失業保険をもらう場合と比べてどちらが得なのでしょうか。
本記事では、失業手当と傷病手当の概要や違いを踏まえて、どちらが得かをケースごとに解説します。また、健康保険の傷病手当金についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
失業保険と傷病手当はどちらが得?
失業保険は、雇用保険における基本手当のことで、就労意思を持ち求職活動を行っている人を対象に支給されます。一方、傷病手当は、ハローワークでの求職申し込みの後に病気やけがで働けなくなった場合に支給される手当です。
そのため、どちらが得かは病気やけがの程度や療養期間の長さによって、以下のように異なります。
【病気の療養期間が14日以内の場合】失業保険
失業保険の受給には、就労の意志と能力があり、求職活動を行っていることが必要です。そのため、求職申し込み以降に病気やけがになってしまった場合、求職活動が難しくなり、受給が難しくなります。
ただし、14日以内に求職活動に復帰できれば失業保険の申請自体は可能です。失業保険を受給するには、4週に1度の失業認定日にハローワークで失業認定を受けなければなりませんが、療養期間と失業認定日が重なる場合は、ハローワークで認定日を変更してもらい、失業認定を継続できます。
【病気の療養期間が15日以上の場合】傷病手当
療養期間が15日以上続く場合には、「傷病手当」の受給対象に該当するため、傷病手当を受給するほうが得です。
傷病手当の日額は失業保険の日額と同額であり、傷病手当の支給日数は失業保険の所定給付日数から、すでに支給された日数を差し引いた残りの日数となります。
なお、基本手当の申し込み後に設定される7日間の待期期間中や退職の理由が自己都合であることによる給付制限中は、傷病手当は基本手当と同様に支給されない点に注意が必要です。
【病気の療養期間が30日以上続いた場合】傷病手当か受給期間の延長
療養期間が30日以上に及ぶ場合は、以下の2つの選択肢があります。
- 引き続き傷病手当を受給し、療養に専念する
- ハローワークに手当の「受給期間延長申請書」を提出する
失業手当の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年間です。しかし、療養が長引く場合は受給期間を最大3年間延長して、合計で最長4年間とすることが可能です。延長を希望する場合は、ハローワークで「受給期間延長申請書」を提出する必要があります。
傷病手当と失業保険の違い
傷病手当は、病気やけがで働けない人を支援するためのもので、健康を回復するために設けられた制度です。
一方、失業保険は、失業後に健康な状態で就労の意思を持って次の仕事を探している人に支給される制度です。
傷病手当と失業保険は両方受給できる?
傷病手当と失業保険は両方同時に受給できません。前述のとおり、傷病手当は病気やけがで働けない人に向けた支援であり、失業保険は健康で求職活動を行っている人に向けた制度であるため、二つの制度は対極にあるためです。
ただし、傷病手当から失業保険に切り替えるなど、「同時」でなければ、両方を受け取ることは可能です。
傷病手当と失業保険の受給条件の違い
傷病手当と失業保険には受給条件に違いがあります。ここでは、それぞれの受給条件を解説します。
傷病手当の受給条件
傷病手当は、ハローワークで求職申込みをした後に、15日以上引き続いて職業に就くことができない場合に支給されます。
つまり、受給には以下の条件を満たす必要があります。
- ハローワークに求職の申し込みをしている
- 失業保険の受給条件を満たしている
- 求職の申し込み後に病気やけがをした
- 病気やけがで15日以上にわたって仕事に就けない
なお、病気やけがが14日以内で回復した場合には、基本手当である失業保険が支給されます。
失業保険の受給条件
失業手当を受け取る条件は次のとおりです。
- 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
- 離職前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(特定受給資格者の場合は1年間に6カ月以上)
- 就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること
失業保険の給付額は、失業前の給与額と年齢によって変動します。また、給付開始までの期間は退職理由によって異なります。
傷病手当と失業保険の受給期間の違い
傷病手当と失業保険には受給期間にも違いがあります。ここでは、それぞれの受給期間について解説します。
傷病手当の受給期間
傷病手当の受給期間は、「基本手当の所定給付日数」から「すでに基本手当が支給された日数」を差し引いた残りの日数です。
基本手当と傷病手当のどちらを受給するかは、以下のように労務不能な期間によって変わります。
- 労務不能な期間が15日未満の場合‥基本手当を受給
- 労務不能な期間が15日以上30日未満の場合‥傷病手当を受給
- 労務不能な期間が30日以上の場合‥基本手当か傷病手当の受給を延長
病気、けが、妊娠、出産、育児などで30日以上働けなくなった場合は、その日数分だけ受給期間を延長でき、延長期間は最長で3年間です。
例えば、所定給付日数が330日と360日の場合、延長できる期間はそれぞれ「3年-30日」と「3年-60日」となります。
失業保険の受給期間
失業保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間(所定給付日数が330日の場合は1年と30日、360日の場合は1年と60日)です。
ただし、病気、けが、妊娠、出産、育児等で30日以上働けない場合は、その期間分だけ受給期間を延長でき、延長できる期間は傷病手当と同様に最長3年間です。
傷病手当と失業保険の受給金額の違い
傷病手当と失業保険の受給金額の違いは以下のとおりです。
傷病手当の受給金額
傷病手当の受給金額は、失業保険の額と同じで、離職前の6か月間の平均給与から算出されます。
|
傷病手当の受給金額 = (離職前の6か月間の総支給額の合計 ÷ 180) × 給付率 |
給付率は退職時の年齢により異なり、45%から80%の間で変動します。
なお、傷病手当の基本手当日額には、以下の表のとおり離職時の年齢区分に応じた上限額が設定されています。
|
年齢 |
基本手当日額の上限 |
|
30歳未満 |
7,065円 |
|
30歳以上45歳未満 |
7,845円 |
|
45歳以上60歳未満 |
8,635円 |
|
60歳以上65歳未満 |
7,420円 |
失業保険の受給金額
失業手当の受給額は「基本手当日額 × 給付日数」で決定します。一般的な受給額は離職前の賃金の5〜8割程度となります。
計算手順は以下のとおりです。
- 賃金日額の計算方法:退職前6カ月の賃金合計 ÷ 180
- 基本手当日額の計算方法:賃金日額 × 給付率
- 基本手当総額の計算方法:基本手当日額 × 給付日数
「基本手当日額」とは、雇用保険で1日当たり受給できる金額のことです。退職前の6カ月間の賃金を180で割った「賃金日額」に、45〜80%の給付率を掛けて算出します。
ここでの賃金には、基本給や残業代、通勤手当、住宅手当などの各種手当は含まれますが、賞与、祝い金、退職金などの臨時的な賃金は含まれません。
なお、給付率は離職時の年齢や退職前の賃金により異なり、賃金が低いほど給付率が高くなります。
傷病手当と失業保険の申請方法の違い
傷病手当と失業保険の申請方法の違いは以下のとおりです。
傷病手当の申請方法
傷病手当は、以下の流れで申請します。
- 「傷病手当支給申請書」を記入する
- ハローワークで申請書を提出する
「傷病手当支給申請書」を記入する
傷病手当を申請するには、申請者本人がハローワークの窓口もしくはホームページで「傷病手当支給申請書」を入手し、以下の必要事項を記入します。
|
記入内容 |
|
|
申請者の個人情報 |
・氏名 ・性別 ・生年月日 |
|
診療担当者の証明 |
・傷病の名称や程度 ・初診年月日 ・傷病の経過 ・傷病のために仕事に就けないと認められる期間 ・診療機関のサインや名称、診療担当者名 |
|
支給申請期間 |
・同一の傷病により受けられる給付 ・上記の期間 ・内職もしくは手伝いをした日、または収入があった日と金額 など |
ハローワークで申請書を提出する
傷病手当支給申請書に必要事項を記入したら、申請者本人が住所地を管轄するハローワークへ書類を提出します。
傷病手当支給申請書は、窓口で直接提出する以外に電子申請も可能です。また、委任状があれば代理人による申請も可能です。
なお、申請を行う際は「傷病手当支給申請書」のほかに「雇用保険受給資格者証」も必要ですので、忘れずに持参してください。
失業保険の申請方法
失業保険は、以下の流れで申請します。
- 必要書類を揃える
- ハローワークで求職を申し込む
- 待機期間を過ごす
- 雇用保険説明会に参加する
- 失業認定日にハローワークを訪れる
必要書類を揃える
ハローワークでの求職申し込み前に、まずは以下の必要書類を準備します。
- 雇用保険被保険者離職票-1・2
- 雇用保険被保険者証
- 証明写真(たて3cm×よこ2.4cm、正面上半身)×2
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 住所・氏名・年齢が確認できる本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1つ)
ハローワークで求職を申し込む
続いて、退職後にハローワークで求職の申し込みを行います。
手続き時の具体的な求職申し込みの流れは次のとおりです。
- 求職申込書に記入する
- 必要書類の提出、職業相談を行う
- 雇用保険説明会の日時が決定する
退職後も求職の意思があり失業保険を受けたい場合は、離職票の提出と求職の申し込みが必要です。
求職の申し込み後に受給資格が決定すると「失業等給付受給資格者のしおり」が交付されます。なお、後述するように、失業保険を受給するには「雇用保険説明会」に参加しなければなりません。開催日時は申請日から7日後以降になるため、忘れずにメモしておきましょう。
待機期間を過ごす
ハローワークで求職の申し込みをして失業保険の受給資格を得ると、7日間の待機期間が設けられる。求職申し込みをした日以降の失業期間が7日に満たない場合、失業保険は給付されません。
なお、この7日間はハローワークが失業状況を調査する期間であり、一切の就労をしないことが求められます。短時間の勤務やアルバイトも就労とみなされるため注意しましょう。
また、失業保険の受給中、所定の給付日数を残して再就職が決まった場合は、再就職手当を受け取れます。ただし、7日間の待期期間中に入社日を迎えると、再就職手当を受け取ることができなくなるので、再就職手当の受給を考えている場合は、入社日との兼ね合いに注意する必要があります。
雇用保険説明会に参加する
失業保険の受給には、求職の申し込み時に案内された雇用保険受給説明会に参加することが必要です。
雇用保険説明会は失業保険の仕組み、受給の流れ、求職方法などが詳しく説明される重要な機会であるため、制度についての理解を深めましょう。
なお、雇用保険説明会への参加時は、以下のものが必要ですので必ず持参してください。
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 印鑑
- 筆記用具
雇用保険説明会が終了すると、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付され、引き続いて初回の失業認定日が案内されます。
失業認定日にハローワークを訪れる
「失業認定日」とは、ハローワークが失業状態にある事実を認定する日です。失業認定を受けるには、失業認定申告書を提出したうえで、就職活動を行っている実績を報告しなければなりません。
通常は、4週間ごとに1度、指定された日が失業認定日となります。また、初回の失業認定日は、原則として離職票を提出した日から約3週間後に設定されます。
傷病手当と傷病手当金の違い
傷病手当と似た給付金に健康保険の傷病手当金があります。ここでは、傷病手当と傷病手当金との違いを理解するために、傷病手当金の概要を解説します。
傷病手当金の受給条件
傷病手当金の受給条件は以下の4つです。
- 業務外の病気やけがで療養中であること
- 療養のため労務不能であること
- 4日以上仕事を休んでいること
- 給与の支払いがないこと
業務上や通勤途中の病気やけがは労働災害保険の対象になります。また、美容整形手術など健康保険の対象外の治療は傷病手当金の対象から除外されます。
労務不能とは、これまでに従事していた業務に就くことができない状態です。労務不能かどうかは、医師の意見や業務内容を考慮して判断されます。
療養開始から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目からが支給対象になります。
傷病手当金の受給期間中に給与が一部支給されている場合は、傷病手当金からその分を減額した金額が支給されます。
傷病手当金の受給金額
傷病手当金の受給金額は以下の計算式で求められます。
|
1日当たりの金額 = 支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2 |
傷病手当金の金額を月給をベースにして標準報酬月額を割り出し、一覧にしたものが以下の表です。
|
月給 |
標準報酬月額 |
傷病手当金(日額) |
傷病手当金(月額) |
|
50,000 |
58,000 |
1,289 |
38,670 |
|
100,000 |
98,000 |
2,178 |
65,340 |
|
150,000 |
150,000 |
3,333 |
99,990 |
|
200,000 |
200,000 |
4,444 |
133,320 |
|
250,000 |
260,000 |
5,778 |
173,340 |
|
300,000 |
300,000 |
6,667 |
200,010 |
|
350,000 |
360,000 |
8,000 |
240,000 |
|
400,000 |
410,000 |
9,111 |
273,330 |
傷病手当金の受給期間
健康保険の傷病手当金が支給されるのは、病気やケガで休んだ期間のうち、最初の3日間を除いた4日目からとなります。
また、受給期間は、手当の支給日数が合計して1年6か月になるまでです。
退職後に健康保険の資格を喪失しても保険の加入期間が継続して1年以上ある場合は、傷病手当金を受け取れる可能性があります。ただし、退職時の会社が加入していた組合によってルールが異なるため、詳しくは専門家への確認が必要です。
傷病手当金の申請方法
傷病手当金の申請方法は次のとおりです。
「健康保険傷病手当金支給申請書」を用意し記入する
勤務先と医療機関に必要な項目を記載してもらう
必要書類を揃え健康保険組合もしくは協会けんぽに提出する
<H2>傷病手当から失業保険に切り替える方法
傷病手当から失業保険に切り替える方法は、「退職後29日以内の場合」と「退職後30日以上経過している場合」で異なります。ここではそれぞれ詳しく解説します。
退職後29日以内の場合
- 退職後29日以内にケガや病気が改善した場合は、一般的な失業保険の申請方法とほぼ同じ。
- 必要な書類を準備し、ハローワークで手続きをおこない、7日間の待期期間後説明会へ参加する。
- その後、自己都合による退職の場合は給付期間を経て、失業認定日にハローワークで失業認定を受けることで受給が始まる。
退職後29日以内に病気やケガが改善し、働ける状態になった場合、失業保険の申請は一般的な手続きとほぼ同じです。以下の流れで手続きを進めます。
- 必要書類の準備
- ハローワークで手続き
- 7日間の待期期間を経て説明会に参加
- 失業認定
失業保険の申請には、離職票(離職票-1および離職票-2)、本人確認書類、マイナンバー、写真(3cm×2.5cm)、銀行口座情報などが必要です。必要書類を持参し、管轄のハローワークで求職申し込みと失業保険の申請を行いましょう。
申請後、まず7日間の待期期間があります。自己都合退職の場合、2ヶ月(2025年4月以降は1ヶ月)の給付制限期間を過ごさなければなりません。
その後、指定された失業認定日にハローワークで失業認定を受けることで、失業手当の受給が始まります。給付制限期間中も定期的な求職活動が必要です。
退職後30日以上経過している場合
退職後30日以上が経過してから失業保険に切り替える場合は、受給資格を維持するために「受給期間延長」の手続きを行う必要があります。通常、失業保険の受給期間は退職後1年間ですが、働けない期間が続いた場合、最大で31年間延長することが可能です。
延長手続きをおこなう手順は、次で詳しく解説します。
失業保険の延長手続きをおこなう手順
失業保険の延長手続きは、条件や手順などが複雑です。ここでは、失業保険の受給期間延長が可能な主な条件と、具体的な手続きの流れについて解説します。
延長できる主な条件
延長できる主な条件は次のとおりです。
- 病気やケガ
- 妊娠や出産
- 親族の介護
病気やケガ
離職後に病気やケガをした場合、治療や療養のために求職活動ができないことがあります。このような場合、医師の診断書や治療計画書などの証明書を提出することで、受給期間の延長を認めてもらえる可能性があります。
延長期間は、病気やケガの治療に必要な期間を考慮して決定されます。
妊娠や出産
妊娠中や出産後すぐの時期に求職活動を行うことは困難です。そのため、失業保険の受給期間を延長することが可能です。
妊娠や出産で延長する場合、母子健康手帳や医師の診断書などを提出しましょう。出産後の育児期間についても考慮され、最大で31年間の延長が認められる場合があります。
親族の介護
要介護状態にある親族を介護する必要がある場合も、受給期間の延長が可能です。介護保険の認定書類や医師の診断書を提出し、介護が必要な状況を証明しましょう。
介護が長期にわたる場合でも、延長期間には上限があるため、ハローワークで詳細を確認することが重要です。
延長の手順
手続きには「直接ハローワークに行く方法」と「郵送で申請する方法」があります。どちらの方法を選ぶかは、個々の状況に応じて決めましょう。
定年退職など特定の理由による場合は、申請期間や必要書類が異なるため、事前に確認が必要です。ここでは、失業保険の受給期間を延長するための具体的な手続きについて詳しく説明します。
直接ハローワークに来所する場合
手続きを迅速に進めたい場合、直接ハローワークに来所しましょう。以下の手順で申請を行います。
- 受給期間延長申請書を受け取る
- 必要書類を用意する
- 必要書類を管轄のハローワークへ持参して提出する
まず、最寄りのハローワークに行き、「受給期間延長申請書」を受け取ります。ハローワークの窓口で相談すれば、記入方法についても詳しく教えてもらえます。
申請には、基本的に「受給期間延長申請書」のほかに、離職票や本人確認書類、印鑑などが必要です。事前に必要な書類を確認しておきましょう。
書類がそろったら、窓口に提出します。書類に不備があると手続きが遅れるため、しっかりと確認してから提出することが重要です。ハローワークの担当者が内容を確認し、問題がなければ申請が完了します。
ハローワークに郵送する場合
ハローワークに直接行けない場合は、郵送で申請することも可能です。以下の手順で進めます。
- 受給期間延長申請書を受け取る
- ハローワークの「雇用保険給付・教育訓練給付窓口」へ電話し、郵送する旨を事前に伝える
- 必要書類を郵送で提出する
郵送で申請する場合でも、まずは「受給期間延長申請書」を入手しましょう。最寄りのハローワークに問い合わせ、書類を送ってもらうよう依頼します。
書類を送付する前に、ハローワークの担当窓口へ連絡し、郵送での申請を希望することを伝えます。電話する際、必要書類や送付先住所について確認しておくと安心です。
申請書類がそろったら、指定された宛先へ郵送します。送付前にコピーを取っておくと、万が一のトラブルにも対応しやすくなります。
定年などが理由の場合
定年退職を理由に失業保険の受給期間を延長する場合、通常の申請と異なる点があるため、注意が必要です。
|
申請期間 |
退職日の翌日から2カ月以内に申請しなければなりません。2カ月を過ぎると延長申請が認められない可能性があるため、早めの手続きが重要です。 |
|
延長可能期間 |
もともとの受給期間は1年間ですが、退職後すぐに就職活動をせずに休養を希望する場合、最長で1年間の延長が可能です。そのため、最大で2年間、失業保険を受け取る権利を保持できます。 |
|
必要書類 |
「受給期間延長等申請書」、「離職票-2」、および本人の印鑑(認印やスタンプ印は不可)が必要です。 |
|
申請方法 |
原則として、本人が直接ハローワークへ出向き、書類を提出する必要があります。 |
失業保険の延長手続きは、期限や必要書類が厳格に決められています。申請漏れや書類の不備があると、延長が認められない可能性もあるため、事前にしっかり準備をして手続きを進めることが大切です。
失業給付の受給期間延長に必要な書類
申請する人の状況によって、必要となる書類は異なります。ここでは、すでに受給手続きを済ませている場合と、まだ手続きをしていない場合とで必要になる書類を紹介します。
受給手続きが済んでいる場合
すでに失業給付の受給手続きを完了している場合、受給資格が認められた状態で延長を申請することになります。そのため、以下の書類を準備する必要があります。
雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)
受給期間延長申請書および延長の理由を証明する書類(例:医師の証明書等)
受給手続きが済んでいない場合
まだ失業給付の受給手続きを行っていない場合、まずは受給資格を確認するための書類と、受給期間延長に必要な書類を準備する必要があります。以下の書類を揃えて、ハローワークへ提出しましょう。
お持ちの全ての離職票-2
受給期間延長申請書
延長の理由を証明する書類
傷病手当金から失業保険に切り替える際の注意点

傷病手当金から失業保険への切り替えを検討する際には、いくつか重要な注意点があります。ここで紹介する2つの注意点を理解し、適切に手続きを行うことが大切です。
手続きが遅れると手当をすべて受け取れなくなる
傷病手当金の受給期間は最長で1年6ヶ月です。受給期間を過ぎると、たとえ病状が回復していなくても手当の支給は終了します。そのため、受給期間が終了する前に、失業保険への切り替え手続きを行うことが重要です。
失業保険の受給期間延長は「30日以上働けない状態が続くこと」が条件です。30日以上継続して働けなくなった日の翌日から申請できます。手続きが遅れると、所定給付日数分の手当をすべて受け取れない可能性があるため、なるべく早めに手続きを行いましょう。
待期期間中はどちらの手当ももらえない
失業保険には7日間の待期期間が設けられています。待期期間中は、失業保険も傷病手当も受け取ることができません。待期期間中はアルバイトも原則として認められていないため、注意が必要です。
自己都合退職の場合、待期期間終了後に2ヶ月(2025年4月からは1ヶ月)の給付制限期間が設けられています。給付制限期間中も、失業保険の支給は行われません。
傷病手当金と失業保険に関するよくある質問
ここからは、傷病手当金と失業保険に関するよくある質問にお応えします。
うつ病で傷病手当金をもらって退職しても、失業保険をもらえますか?
うつ病で傷病手当金を受給しながら退職した場合でも、失業保険(基本手当)の受給は可能です。
退職後にうつ状態が回復してすぐに働ける状態であれば、失業保険の受給手続きを進めることができます。
一方で、退職時点においてうつ病の療養が必要で働けない場合は、失業保険の受給を延長する手続きを行いましょう。まずは治療に専念することが重要です。
傷病手当金の受給中にアルバイトできますか?
傷病手当金の受給中にアルバイトや副業を行うことは原則として認められてはいません。アルバイトを行うことで「労務に従事できる」と判断されると、傷病手当金の支給が停止されてしまいます。
失業保険や傷病手当金はパートや派遣でももらえますか?
パートや派遣でも、受給の条件を満たせば失業保険や傷病手当金をもらうことは可能です。
まとめ
失業保険と傷病手当は、状況に応じてどちらを選ぶべきか異なります。病気やケガの療養期間が14日以内なら失業保険を受給できますが、15日以上続く場合は傷病手当が適しているでしょう。
療養が30日以上になると、傷病手当を継続するか失業保険の受給期間を延長する選択肢があります。両方を同時に受け取ることはできませんが、病状が回復すれば失業保険に切り替え可能です。また、健康保険の傷病手当金とは制度が異なるため注意が必要です。
失業保険や傷病手当の申請をスムーズに進めるには、制度の仕組みを理解し、適切な手続きを行うことが大切です。しかし、申請の流れや必要書類に不安を感じる方も少なくありません。不安がある方は、「社会保険給付金サポート」をご利用ください。専門家のアドバイスを受けることで、申請の不備や受給漏れを防ぎ、スムーズに給付金を受け取ることが可能です。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
おすすめの関連記事
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 新型コロナウイルスについて
- 社会保険について
- 退職代行について
- 税金について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
障害年金を知ろう
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは必須?スムーズな業務引き継ぎのポイント
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
テーマ
- クレジットカード
- 資格取得
- 退職願
- 職業訓練受講手当
- 自己PR
- 社会保険給付金
- 退職代行
- アルバイト
- 精神疾患
- 退職届
- インフルエンザ
- 確定申告
- 職業訓練受講給付金
- 退職代行サービス
- 雇用保険
- うつ病
- 面接
- 感染症
- 保険料
- 退職給付金
- ブラック企業
- 健康保険
- 統合失調症
- 障害手当金
- 引っ越し
- 社会保障
- ハローワーク
- ハラスメント
- 年金
- 契約社員
- 自己都合
- 社宅
- 就職
- 就業手当
- パワハラ
- 転職活動
- 弁護士
- 会社都合
- 障害者手帳
- 労働基準法
- 傷病手当
- モラハラ
- 転職サイト
- 公的貸付制度
- 失業給付
- 精神保険福祉手帳
- 雇用契約
- 退職コンシェルジュ
- セクハラ
- 職務経歴書
- 生活福祉資金貸付制度
- 新型コロナウイルス
- 労災
- 内定
- 社会保険給付金サポート
- 障害年金
- 人間関係
- 通勤定期券
- 有給消化
- 産休
- 就労移行支援
- 雇用保険サポート
- 引き継ぎ
- スタートアップ
- 不支給
- 休職
- 育児休暇
- 業務委託
- 退職手当
- 給与
- 転職
- 等級
- 免除申請
- 解雇
- 社会保険
- 残業代
- 違法派遣
- 離職票
- 適応障害
- 大企業
- 福利厚生
- 退職金
- 派遣契約
- 労務不能
- 住宅確保給付
- 中小企業
- 失業手当
- 会社都合退職
- 障害厚生年金
- 傷病手当金
- 給付金
- ベンチャー企業
- 就職困難者
- 自己都合退職
- 失業保険
- 年末調整
- 職業訓練
- 会社倒産
- 再就職手当
- 退職
- ブランク期間
- 障害者控除
- 再就職
- 退職勧奨
- 転職エージェント
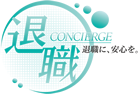




 サービス詳細
サービス詳細