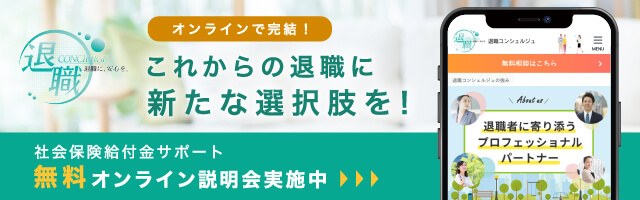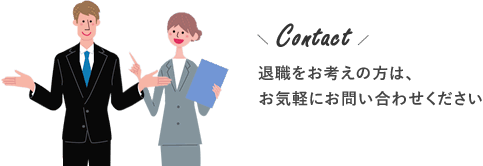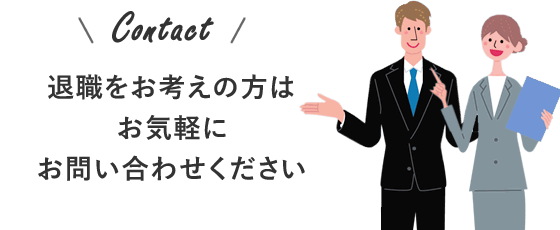2025.03.06
社会保険について
失業保険と扶養どっちが得?お得になるケースと両方実現するための手順とは

「退職後に、失業保険をもらうのと扶養に入るのとどっちがお得なのか」と悩む方は少なくありません。失業保険と扶養は、どちらも退職後に利用可能な制度ですが、自分にはどちらが最適なのかが分かりにくいこともあるでしょう。
本記事では、失業保険と扶養の意味やメリット・デメリットを解説します。失業保険をもらいながら扶養に入る手順やお得になるケースもご紹介しますので、退職予定の方や退職後にお悩みの方は参考にしてください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
失業保険とは

失業保険は、退職後に受け取ることができる給付です。ここでは、失業保険の概要とともに受給条件や金額、受給可能な期間を解説します。
失業保険の概要
失業保険は、雇用保険(失業保険)に入ることで失業時に給付を受けられる制度です。労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、生活及び雇用の安定を図るために必要な給付が行われます。
失業保険は、退職後、次の仕事に就業するまでの失業期間に支給されるため、その間は金銭面での不安を受けることなく生活を送ることができます。
ただし、受給には一定の条件があり、退職理由により受給金額が異なるため注意が必要です。
失業保険の受給条件
失業手当を受け取るための条件は次の通りで、すべての条件を満たさなければなりません。
- 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
- 離職前の2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(特定受給資格者と特定理由離職者の場合は1年間に6カ月以上)
- 就労意志と能力があるものの失業中で、求職活動を行っていること
一方で、以下のような人は受給条件がないものとされ、失業保険を受給できません。
- 妊娠・出産・育児などのために、すぐに就労できない人
- 病気・ケガ・障害などのために、すぐに就労できない人
- 就職するつもりがない人
- 家事に専念している人
- 学業に専念している人
- 会社などの役員に就任している人
- 雇用保険に加入していなかった自営業の人
失業保険は、失業すれば必ず受けられるものではありません。受給を検討する場合は、自身が受給資格を満たすかどうか、各条件を確認することが大切です。
失業給付金の受給金額
失業手当の受給額は「給付日数 × 基本手当日額」で計算されます。ただし、日数や基本手当日額は、離職状況に応じて異なるため、必ず確認してください。
「基本手当日額」は、雇用保険で1日当たり受給できる金額です。具体的な金額は、退職前6カ月間の賃金(ボーナスを除く)を180で割った「賃金日額」に、50〜80%の給付率を掛けて算出されるため、離職前の賃金の5〜8割程度となるのが一般的です。
これらを計算式に表すと次の通りになります。
- 賃金日額の計算方法:退職前6カ月の賃金合計 ÷ 180
- 基本手当日額の計算方法:賃金日額 × 給付率
- 基本手当総額の計算方法:基本手当日額 × 給付日数
給付率は、離職時の年齢や退職前の賃金日額によって異なり、離職前の収入が低かった場合ほど高い割合になります。
また、受給額には上限と下限が設けられており、以下の表のように上限は年齢によって異なります。
(令和6年8月1日現在の上限額)
|
30歳未満 |
7,065円 |
|
30歳以上45歳未満 |
7,845円 |
|
45歳以上60歳未満 |
8,635円 |
|
60歳以上65歳未満 |
7,420円 |
失業給付金の受給期間
雇用保険(基本手当)の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間(短期雇用特例被保険者は6カ月間)です。ハローワークで失業保険の受給手続きを行った後、失業状態の日について、所定給付日数(90〜360日)を限度として支給されます。
受給期間の経過後は、所定給付日数分を受け取っていなくても支給は終了します。離職後、早めに手続きを行うようにしましょう。
失業保険を受給するメリット

失業保険を受給する主なメリットは、以下の2つです。
- 働けなくなっても経済的に安定する
- 生活費を補いながら転職活動に集中できる
それぞれ詳しく解説します。
働けなくなっても経済的に安定する
失業保険を受給すると、万が一、退職後に病気・ケガで働けなくなった場合であっても経済的な安定が得られます。企業に勤めていた期間に十分な貯蓄ができていたのであれば、退職後に働けなくなると経済的な心配が生じるでしょう。
失業保険を受給することで収入が確保できると金銭面での不安が軽減されて、療養に専念できる点がメリットです。
生活費を補いながら転職活動に集中できる
失業保険を受給することで、生活費を補いながら転職活動に集中できるのもメリットです。十分な貯蓄がない状態で退職すると、金銭的な問題から自分に適していない職場や条件の悪い仕事を選ぶかもしれません。
一方で、失業手当を受け取れば経済的な不安が軽減され、資格取得やスキルアップの勉強に時間を使い、転職準備を充実させられるでしょう。焦らずに自分に合った仕事や職場を選ぶ余裕も生まれます。
失業保険を受給するデメリット
失業保険の受給にはデメリットも存在します。ここでは、3つのデメリットをご紹介します。
- 受給に関してさまざまな制約が発生することもある
- 受け取るためには手間と時間がかかる
- 転職に対する意欲が弱まってしまうこともある
受給に関してさまざまな制約が発生することもある
失業保険をはじめとする社会保険給付金を受け取り続ける場合は受給に関してさまざまな制約が生じます。失業手当の金額は勤務していたときの賃金の5〜8割となるため、家計を見直し、出費を抑えて生活する必要があるでしょう。
なお、失業保険を受給している間は制限があるものの、一定の条件下で働くことは可能です。
また、失業手当の受給期間中に再就職が決まった場合、状況によっては再就職手当を受け取れます。再就職手当は、残りの受給期間に支給される予定だった金額の一部が受け取れる制度です。ただし、長期間にわたって失業保険を受け取っているケースでは再就職手当がもらえない場合があるため注意が必要です。
受け取るためには手間と時間がかかる
失業保険を受け取るには、多くの手間と時間がかかることもデメリットです。
必要書類を正確に揃え、病院やハローワークでの手続きを自分で進めなければならないため、体調不良や介護がある人には負担が大きいといえるでしょう。
給付金は自動では振り込まれず、給付を受けるには自分で申請手続きを行う必要があることにも留意が必要です。
また、失業保険は失業後すぐに受け取ることができません。退職後にハローワークで手続きを行わなければならず、7日間の待期期間が設けられます。自己都合退職の場合は、待期期間に加えて2か月の給付制限期間が設けられており、この期間内は手当が支給されません。申請から2ヶ月以上後に支給される可能性があることを理解しておきましょう。
転職に対する意欲が弱まってしまうこともある
失業手当を受ける結果、かえって転職に対する意欲が弱まってしまうケースは少なくありません。
給付金があることに安心して再就職の意思が薄れてしまうと、再就職までの空白期間が長くなり採用担当者に不審を抱かれる可能性もあるでしょう。
失業手当などの社会保険給付金に頼りすぎず、目標を設定しながら積極的に転職活動を進めることが大切です。
扶養とは
退職後に家族の扶養に入ることを選択する方もいるでしょう。そもそも「扶養」とはどのような制度なのでしょうか。ここでは税法上と社会保険上における扶養の定義を解説します。
税法上の扶養
税法上の扶養は、扶養家族の給与年収が103万円以下の場合に適用される制度です。扶養に入ることで、所得税や住民税の負担が軽減されます。
扶養家族の年収が103万円を超えると、扶養から外れて規定通りの納税をしなければなりません。一方で、扶養を維持すれば、税負担の軽減が受けられる点がメリットです。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、自分で保険料を支払わなくても健康保険や国民年金保険に加入できる制度です。
健康保険における扶養は、例えば、児童自身は保険料を支払っていなくても、健康保険証で医療サービスを受けられるケースがわかりやすいでしょう。このケースでは、児童が被扶養者として健康保険上の扶養に入っているため、自身で保険料を支払う必要はありません。ただし、成長して扶養から外れた場合は、自身で保険に加入し、保険料を支払わなければなりません。
また、厚生年金保険の扶養に入るケースでは、国民年金の支払いが免除されるため、保険料負担を軽減できるメリットがあります。
扶養の対象になるもの
ここからは、扶養の対象となる範囲を解説します。
扶養控除
扶養控除とは、所得税に関する控除で、年間の合計所得が38万円以下の子や親などと生計を共にしている場合に適用されます。
具体的な控除額は、年齢や同居の有無で異なります。
|
扶養対象者の年齢・同居の有無 |
控除額 |
|
一般の控除対象扶養親族(16歳以上) |
38万円 |
|
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) |
63万円 |
|
老人扶養親族(70歳以上・同居) |
58万円 |
|
老人扶養親族(70歳以上・別居) |
48万円 |
なお、配偶者は扶養控除の対象外となり、後述する配偶者控除または配偶者特別控除が適用されます。
配偶者控除
配偶者控除は、納税者に一定の配偶者がいる場合に適用される制度です。控除額は納税者の所得と控除対象となる配偶者の年齢で決定されます。納税者の所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は適用外となります。
【70歳未満の配偶者】
|
納税者の合計所得金額 |
控除額 |
|
900万円以下 |
38万円 |
|
900万円超950万円以下 |
26万円 |
|
950万円超1,000万円以下 |
13万円 |
【70歳以上の配偶者】
|
納税者の合計所得金額 |
控除額 |
|
900万円以下 |
48万円 |
|
900万円超950万円以下 |
32万円 |
|
950万円超1,000万円以下 |
16万円 |
配偶者控除を受けるには、配偶者が以下の条件を満たす必要があります。
- 法律上の配偶者であること(内縁関係は対象外)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間合計所得48万円以下であること
- 事業専従者ではないこと(青色申告の事業専従者や白色申告の事業専従者でない)
青色申告者の事業専従者として給与を受ける場合、配偶者控除は受けられません。ただし、事業専従者控除が適用されます。
また、配偶者控除が適用されない場合でも、後述する配偶者特別控除が利用できる可能性はあるので、該当するかどうか確認しておきましょう。
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、配偶者の年間所得が48万円超133万円以下の場合に適用される制度で、133万円超で対象外となります。
なお、所得は、給与収入から控除を差し引いた金額で、収入とは異なります。そのため、社会保険における収入要件と容易には比較できない点に留意してください。
一例に、給与収入が130万円の場合、所得控除後の所得金額が27万円なら配偶者控除の対象となります。一方で、収入要件では130万円で判断される点に注意が必要です。
健康保険
健康保険の被扶養者になるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 被保険者と同一世帯に属している
- 年収130万円未満(60歳以上・障害年金受給者は180万円未満)
- 被保険者の年収の2分の1未満である
これらの要件を満たさない場合は、各自で健康保険に加入する必要があり、保険料が生じます。
また、収入が基準額を少し超えるケースでは支払うべき保険料が増えて手取額が減少するため、収入の調整にも注意が必要です。
厚生年金
厚生年金保険でも、第2号被保険者(会社員・公務員)の配偶者は、保険料を追加せずに第3号被保険者として国民年金に加入できます。
第3号被保険者となる要件は以下のとおりです。
- 第2号被保険者の配偶者である
- 20歳以上60歳未満
- 年収130万円未満(60歳以上・障害厚生年金受給者は180万円未満)
なお、第2号被保険者と同居している場合は、配偶者の収入が被保険者の収入の半分未満である必要があります。これらの条件は、健康保険の要件と同様です。
扶養に入るメリット
税法上や社会保険上の扶養に入るメリットは、以下の3つです。
税負担が軽減する
扶養される人は社会保険料が免除される
家族単位でみた場合、社会保険料の負担が抑えられる
それぞれ解説します。
税負担が軽減する
税法上では、家族を扶養に入れると、扶養者の税金が抑えられる点がメリットです。配偶者を扶養に入れる場合は配偶者控除・配偶者特別控除が適用され、親を扶養に入れる場合は扶養控除が適用されるからです。
ただし、扶養される人は所得が一定額以下である必要があり、所得が少ないほど税負担も少なくなります。つまり、扶養する側、される側の双方に税負担軽減のメリットがあります。
扶養される人は社会保険料が免除される
被扶養者は、社会保険料の支払いが免除されます。通常、公的医療保険は強制加入であり、会社の健康保険に加入できない場合は国民健康保険に加入して保険料を納めなければなりません。しかし、働いていない人でも家族の健康保険の被扶養者になれば、自分で保険料を支払う必要がなくなります。
先述した条件を満たしたうえで配偶者の扶養に入れば、国民年金保険料も免除され、社会保険料の負担が軽減されるのもメリットです。
家族単位で見た場合、社会保険料の負担が抑えられる
家族単位で見た場合に、社会保険料の負担が抑えられるのも大きなメリットといえるでしょう。
なぜなら、健康保険では被扶養者が増えても、被保険者の保険料は変わらないためです。配偶者を扶養に入れても、厚生年金保険料は増加しないため、その分の負担を軽減できます。
扶養に入るデメリット
親族の扶養に入ることには以下の3つのデメリットがあります。各デメリットの詳細を解説します。
- 年収が制限される
- 将来の年金額が少なくなる
- 傷病手当金を受け取れない
年収が制限される
扶養に入ることの大きなデメリットは年収が制限されることです。
税法上の扶養に入るには年収103万円以下(配偶者控除)または201万円以下(配偶者特別控除)が条件となっています。また、社会保険上の扶養は、年収130万円未満が基準となります。
扶養のメリットを得るには年収の上限が制限されるため、働く時間を増やしにくい状況が生じることがあるでしょう。
将来の年金額が少なくなる
将来的に受給できる年金額が少なくなることも扶養に入るデメリットです。
パートやアルバイトで働く場合は、配偶者の扶養に入ることで勤務先の社会保険に加入しない選択肢があります。この場合、自身は厚生年金に加入しないため、将来の年金額が少なくなる可能性が生じるからです。
また、国民年金のみだと満額でも月約6.6万円程度に限られるため、老後の生活資金に不安が生じることもあるでしょう。
傷病手当金を受け取れない
健康保険に加入していると、病気やケガで休職した際に傷病手当金が支給されます。しかし、被扶養者が病気やケガで求職しても傷病手当金は受け取れないため、収入が途絶える可能性があります。
扶養内で働く場合は、病気やケガへの備えが必要です。貯蓄を増やしておく、個人的に医療保険に加入しておくなどの対策を取ると良いでしょう。
失業保険をもらいながら扶養に入るための条件
失業保険を受給していても、年収が130万円未満であれば、社会保険の扶養に入ることは可能です。
妻が夫の扶養に入る際は「収入の見込み」が重要になります。失業保険の基本手当日額が3,611円未満であれば扶養対象となります。一方で、基本手当日額が3,611円以上だと年収が130万円を超えるため扶養に入れません。
なお、失業保険の受給額も収入として計算される点に注意が必要です。
失業保険をもらいながら扶養に入る手順
失業保険をもらいながら扶養に入る手順は以下の通りです。各手順について詳しく解説します。
- 必要書類を揃える
- 扶養に入る
- ハローワークで求職を申し込む
- 待期期間を過ごす
- 雇用保険説明会に参加する
- 失業認定日にハローワークを訪れる
1. 必要書類を揃える
ハローワークでの求職を申し込む前に、扶養者認定に必要な書類を準備します。必要書類は次の通りです。
- 雇用保険被保険者離職票-1・2
- 雇用保険被保険者証
- 証明写真(たて3cm×よこ2.4cm、正面上半身)×2
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 住所・氏名・年齢が確認できる本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1つ)
扶養に入るために必要な書類は次の通りです。
- 扶養者の健康保険の被扶養者届(異動届)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 収入証明書(源泉徴収票や給与明細、失業手当の受給証明書など、収入を証明するもの)
- 退職証明書や離職票(退職している場合)
- 失業手当の受給終了証明(失業手当の受給が終了していることを示す書類)
- 住民票など、扶養に入る本人と扶養者の関係が記載されているもの(場合によって必要)
2. 扶養に入る
書類が準備できれば、扶養認定の手続きを行います。事前に被扶養者となる資格があるかどうか、要件を確認しましょう。
配偶者や親族を社会保険の扶養に入れる際は、事実発生から5日以内に「被扶養者(異動)届」と必要書類を年金事務所や事務センターへ提出します。
配偶者を扶養に入れる場合は「被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届」に記入し、厚生年金の第3号被保険者への切り替えも同時に行います。
各書類の提出は、窓口持参のほか、郵送、電子申請、CD/DVDなどの電子媒体を通じても可能です。
3. ハローワークで求職を申し込む
退職後に、ハローワークで求職の申し込みを行います。一般的な流れは次の通りです。
- 求職申込書に記入する
- 必要書類の提出、職業相談を行う
- 雇用保険説明会の日時が決定する
求職の意思があり、失業保険を受けたい場合は、離職票の提出と求職の申し込みが必要です。求職の申し込み後、受給資格が決定すると「失業等給付受給資格者のしおり」が交付されます。
後述する「雇用保険説明会」の日時案内は申請日から7日後以降になるため、忘れずにメモしておき、失業等給付受給資格者のしおりとともに保管しておきましょう。
4. 待機期間を過ごす
ハローワークで失業保険の受給資格が得られれば、7日間の待機期間が設けられます。退職理由が会社都合であっても、求職申し込みをした日からの失業期間が7日に満たない場合は給付されません。
待機期間として定められた7日間は、ハローワークが失業状況を調査する期間です。この期間は一切の就労をしないことが求められ、短時間の勤務やアルバイトをした場合であっても就労とみなされるため注意してください。
また、待期期間の経過後、失業保険の給付内の一定期間に再就職すると再就職手当を受け取れるケースがあります。ただし、待期期間中に入社日を迎える場合は、再就職手当を受け取れなくなるため、再就職手当の受給を目指している場合は、留意が必要です。
5. 雇用保険説明会に参加する
失業保険を受給するには、求職の申し込み時に案内された雇用保険受給説明会に参加する必要があります。
雇用保険説明会では、失業保険の仕組みや受給の流れ、求職方法などが詳しく説明されるため、理解を深めておきましょう。
雇用保険説明会の参加時は、次のものを忘れず持参してください。
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 印鑑
- 筆記用具
説明会終了後に、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が交付されます。また、初回以降の失業認定日も案内されるため、スケジュールを確認しておきましょう。
6. 失業認定日にハローワークを訪れる
失業保険の受給中は、失業認定日にハローワークを訪れる必要があります。「失業認定日」とは、ハローワークが失業の事実を認定する日のことで、失業認定申告書を提出して、就職活動の実績を報告しなければなりません。
通常は4週間ごとに1回のペースで指定された日が失業認定日となります。なお、初回の失業認定日は、離職票を提出した日から起算して約3週間後に設定されます。
失業保険が得になるケース
失業保険を受給するケースと扶養に入るケースとでは、どっちが得になるのでしょうか。まずは、失業保険を受け取る方が得になる3つのケースをご紹介します。
会社都合で退職した
失業保険を受け取る方が得になるケースの一つめは、退職理由が会社都合だった場合です。
前述のとおり、自己都合で退職するケースでは、7日間の待期期間に加えて2か月の給付制限期間が設けられ、その間は失業保険を受け取れません。
一方で、会社都合による退職では失業保険の給付制限期間が設けられず、7日間の待期期間後すぐに受給できるため、扶養に入るよりも得になります。
雇用保険の加入期間が長い場合
雇用保険の加入期間が長い場合も、扶養に入るよりも得です。なぜなら、失業保険の受給日数は雇用保険の加入期間や年齢によって異なり、加入期間が長いほど受給日数が増えるからです。
失業保険の受給日数は次の通りです。
|
加入期間 |
受給日数 |
|
1年未満 |
受給不可 |
|
1年以上10年未満 |
90日 |
|
10年以上20年未満 |
120日 |
|
20年以上 |
150日 |
雇用保険の加入期間が長い場合は、日数だけでなく受給総額も増えるため、失業保険を利用する方が経済的に有利になります。
再就職に向けて活動している
失業保険は再就職に向けて活動している期間に受け取れる給付金であり、再就職すれば収入が得られるため結果的にお得です。
失業保険を受け取るには、求人応募や面接などの行動が必要になるため、実際に再就職を目指している場合には扶養に入るよりも失業保険を受給する方が適しているでしょう。
また、再就職を検討している方にとって失業保険は一時的な収入源となるため、扶養よりも経済的に有利になります。
扶養が得になるケース
ここからは、失業保険を受給するよりも扶養に入る方が得になる3つのケースをご紹介します。
自己都合退職した
自己都合退職をした場合、7日の待機期間に加えて失業保険の受給まで2ヶ月(2025年4月からは1ヶ月)の給付制限期間が設けられます。期間中は収入が途絶えるため、一時的に扶養に入る方がお得な場合があります。
扶養制度の利用は、失業保険の給付制限期間中でも可能です。その間の税金や保険料の負担を減らせるため、収入がない期間の負担軽減として扶養制度を活用するのがおすすめです。
妊娠・出産で退職した
妊娠・出産で退職して、すぐに再就職しない場合は、配偶者の扶養に入る方が保険料の負担が軽減されるためメリットが大きくなります。
妊娠中や出産後は就職活動が難しくなり、失業保険も受けられないため、扶養に入る方が現実的といえるでしょう。また、妊娠・出産後も保険料負担を抑えられるため、退職のタイミングで扶養の手続きを検討するのがおすすめです。
<h3>退職して専業主婦(主夫)になる
退職後に再就職の予定がなく専業主婦(主夫)になる場合は失業保険を受給できないため、配偶者の扶養に入ることが一般的です。
扶養に入ることで健康保険や年金の保険料負担がなくなり、家計の負担が軽減されます。ただし、再就職の可能性がある場合もあるでしょう。状況によって扶養に入るかどうかを判断し、必要に応じて手続きを進めることが重要です。
失業手当を受給しながら扶養に入ってしまったら

失業手当を受給しながら扶養に入ってしまった場合、どのような対応を取る必要があるのでしょうか。ここでは、具体的な対応策を解説します。
扶養を外して健康保険料を返納する
一つめの対応策は、扶養を外して健康保険料を返納することです。例えば、妻が夫の扶養に入っている状態で「130万円の壁」を超えた場合、夫は保険組合に「資格喪失届」を提出して、扶養を外さなければなりません。
また、扶養が外れている期間に妻が先に発行されていた保険証を使用した際の、保険適用分の医療費は無効となり、妻が7割分を夫の保険組合に返納する必要があります。
この場合、妻は国民健康保険などに加入し直し、過去分の保険料を支払わなければなりませんが、加入手続きの完了後に国民健康保険から7割分の医療費相当額が返金されます。
国民年金の支払いが必要になる
退職後は国民年金を支払う必要があります。誤って扶養に入っていた場合は、遡って「第1号被保険者」への切り替え届出と国民年金保険料の支払いを行わなければなりません。
なお、届出が2年以上遅れると、2年より前の期間は「未納期間」となり、保険料を納めることができないため注意が必要です。
ただし、失業中は申請によって国民年金の特例免除を申請可能です。この期間は、加入期間に算入されるものの、将来の年金額は免除分だけ減少します。また、納付を先延ばしにする「納付猶予」制度も利用できるので、必要に応じて活用しましょう。
まとめ
失業保険は、雇用保険に加入していた労働者を対象に、失業や雇用継続が困難な場合に一定の期間にわたって支給される給付です。一方で、扶養は、税法上や社会保険上で認められている制度で、扶養に入ると税金の負担や健康保険、国民年金保険などの保険料を支払う必要がなくなります。
そのため、失業保険の受給と扶養に入るケースでは、どっちが得か悩む方もいるでしょう。一般に、会社都合での退職や雇用保険の加入期間が長い場合は失業保険の受給が得になります。一方で、自己都合や妊娠・出産を理由に退職した場合は、失業保険の給付制限がかかっている間は扶養に入る方がお得です。
「自分では、どっちがお得なのかわからない」「手続きが難しい」とお考えの方は、「社会保険給付金サポート」のご利用をおすすめします。経験豊富なプロの選任スタッフが、丁寧にヒアリングのうえ、給付金請求手続きをサポートいたしますので、ぜひご相談ください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
おすすめの関連記事
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 新型コロナウイルスについて
- 社会保険について
- 退職代行について
- 税金について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
障害年金を知ろう
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは必須?スムーズな業務引き継ぎのポイント
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
テーマ
- クレジットカード
- 資格取得
- 退職願
- 職業訓練受講手当
- 自己PR
- 社会保険給付金
- 退職代行
- アルバイト
- 精神疾患
- 退職届
- インフルエンザ
- 確定申告
- 職業訓練受講給付金
- 退職代行サービス
- 雇用保険
- うつ病
- 面接
- 感染症
- 保険料
- 退職給付金
- ブラック企業
- 健康保険
- 統合失調症
- 障害手当金
- 引っ越し
- 社会保障
- ハローワーク
- ハラスメント
- 年金
- 契約社員
- 自己都合
- 社宅
- 就職
- 就業手当
- パワハラ
- 転職活動
- 弁護士
- 会社都合
- 障害者手帳
- 労働基準法
- 傷病手当
- モラハラ
- 転職サイト
- 公的貸付制度
- 失業給付
- 精神保険福祉手帳
- 雇用契約
- 退職コンシェルジュ
- セクハラ
- 職務経歴書
- 生活福祉資金貸付制度
- 新型コロナウイルス
- 労災
- 内定
- 社会保険給付金サポート
- 障害年金
- 人間関係
- 通勤定期券
- 有給消化
- 産休
- 就労移行支援
- 雇用保険サポート
- 引き継ぎ
- スタートアップ
- 不支給
- 休職
- 育児休暇
- 業務委託
- 退職手当
- 給与
- 転職
- 等級
- 免除申請
- 解雇
- 社会保険
- 残業代
- 違法派遣
- 離職票
- 適応障害
- 大企業
- 福利厚生
- 退職金
- 派遣契約
- 労務不能
- 住宅確保給付
- 中小企業
- 失業手当
- 会社都合退職
- 障害厚生年金
- 傷病手当金
- 給付金
- ベンチャー企業
- 就職困難者
- 自己都合退職
- 失業保険
- 年末調整
- 職業訓練
- 会社倒産
- 再就職手当
- 退職
- ブランク期間
- 障害者控除
- 再就職
- 退職勧奨
- 転職エージェント
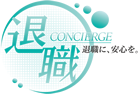




 サービス詳細
サービス詳細